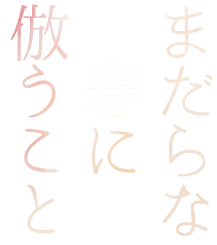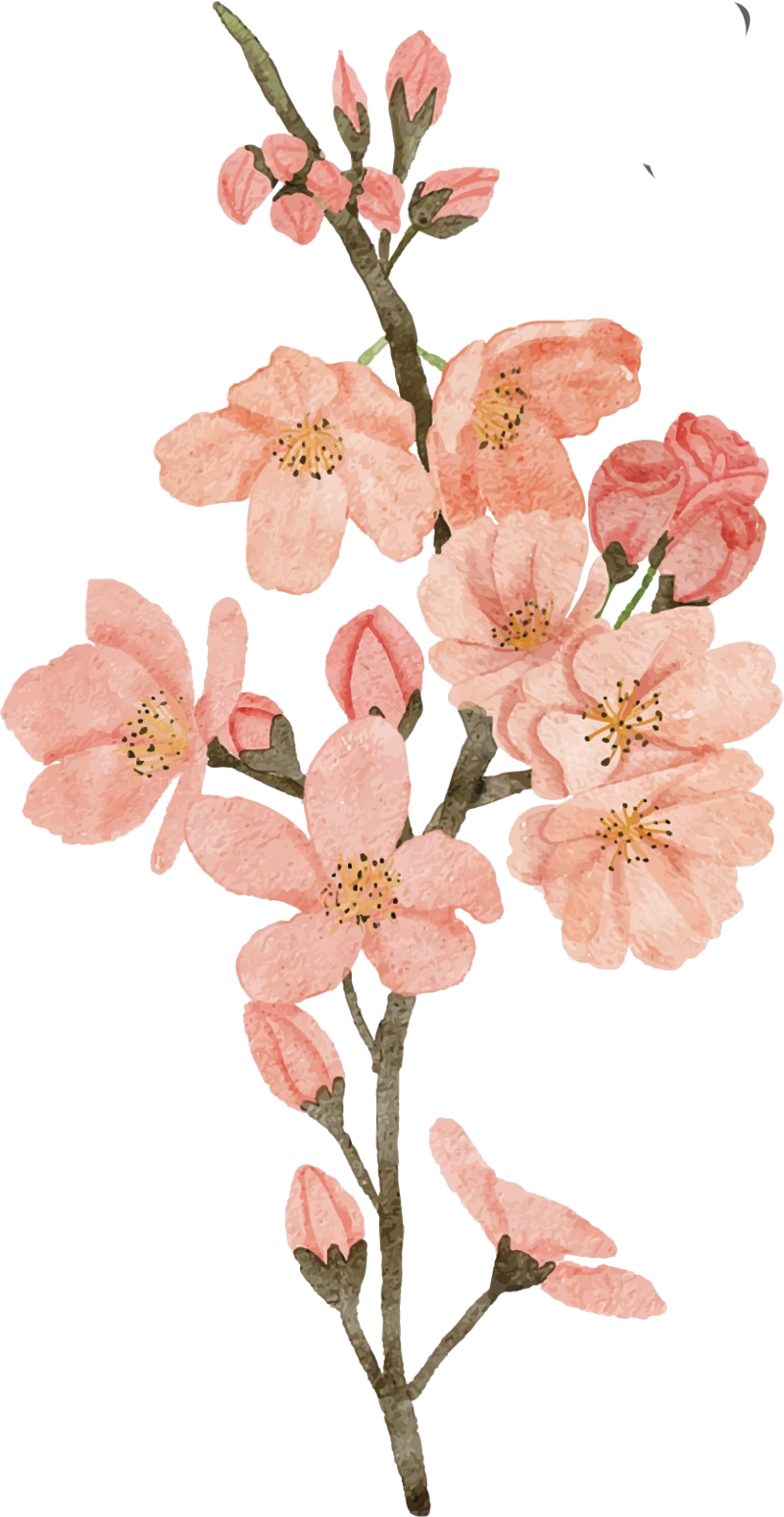正確な日数はわからないのだが、ようやく取り戻した『体』というもの、重力のおもみというものをどうも忘れていたようだった。空気が違う、風景が違う、光が違う。そう思ってはいたが、本来の肌で受け取る感覚はまた別のもので、かつ、乙骨と生活していると思ってはいたが実際に生活していなかったこと。つまり知覚していなかった日常茶飯事への解像度の薄さが、今になって真にせまってしまった。
洗面所の化粧品の使われた形跡がまばらであること、自分が二階のベッドで眠るとき乙骨も一階で眠っておりその寝息が薄っすらと聞こえること、互いの風呂上りの気まずさや、ふとした瞬間に目が合って何を話せばいいかわからなくなること。
乙骨のいう魂だけの状態、生霊のときはそういうこまごまとしたことは気にかからなかった。彼女は一日の大半は意識がおぼろげで眠っている状態だったし、そのときの記憶はない。だから、それは生活ではなかったのだ。
『棺那比』を内部へ取り込んだことで、乙骨が彼女を殺し、日本から連れ出した理由は解決した。けれど今の別問題は、リカが呪力で無理やり日本を抜け出してきてしまったことだ。つまり、空港を経由していないので、彼女は今パスポートを持っていない。更にいえば、大学生の時に取得したパスポートは五年経過しているため、失効しているだろう。
乙骨は「どうにかなる」と言ってあまり焦りを見せなかったし、実際に一週間ほどで帰国の手筈が整うと聞いた。けれど逆に言えば一週間はここで、この国で、乙骨と二人で生活することになる。乙骨への恐怖心は薄らいでいたが、異性と二人で過ごすということに若干の警戒心を持たなかったわけでも、緊張しないわけではなかった。
そんな彼女の様子がわかったのだろう。乙骨は申し訳なさそうに、自分が別のホテルでも泊まりに行くか、行ってもらうことができればいいが、彼女の内部に取り込まれた『棺那比』の経過観察のためには、なるべくそばにいたほうがいいことを説明した。乙骨の説明からすれば、元々『棺那比』は彼女の生家が管理して呪霊である。乙骨に謝らせるのもおかしな話のように思えて、とりあえず何事もなく一週間が過ぎることを願った。
乙骨が隣家からボートを借りたと言って彼女を湖へ誘ったのは、同居を始めて二日目のことだった。
隣家の夫婦喧嘩はなあなあのうちに終了したようで、『棺那比』の放った呪いも乙骨が祓ったため子どもの父親の不調も回復している。子どもにも呪霊から受けた後遺症などもなく、元気だった。
「いつもよく眺めていたようなので、よければ」
『棺那比』が暴走する可能性を考えれば、観光地などに行くわけにもいかない。なので、せめて、よければ。乙骨がそう困り顔で重ねるので、彼女は嫌とも言えず頷いた。子どもの父親は先んじてボートを湖に浮かべてくれていたようで、まず乙骨がボートに乗り込んで、それからこちらへ手を伸ばしてくる。照れ臭く思いながらその手を取って、船底へ踏み出す。乙骨は以外に思えるほどしっかりとした力で体を支え、彼女に座るように言った。
「僕も受け売りですけれど、この辺りの地域は、あちこちにこういう小さな湖があるみたいですよ」
「へえ」
乙骨の言葉に相槌を打ったあと、何を言っていいのか、全くわからなくなってしまった。ぎぃ、ぎ、と乙骨がオールを動かす音だけがしている。幽霊のような状態だったときは、記憶はあるが本当にぼんやりとした状態だったようだ。こういう気まずさを逃げ場のないほど、感じた覚えがない。視界の端でちらりと乙骨を見れば、彼も困ったように眉を下げる。気を遣われていることがわかり、ますます申し訳ない気持ちになった。
「乙骨さんは、……好きな食べ物なんですか?」
「好きな食べ物?」
怪訝そうな顔をする。乙骨はどうして呪術師をしているのかだとか、呪力というものを知ったときどう感じたのかだとか、聞きたいことはいくつもあったが、センシティブすぎる話題のような気もした。他に場を持たせられて、ちょうどいい話題が思いつかず、お見合いのようなクソ質問をしてしまった。
怪訝そうな顔をしていた乙骨は、それから破顔して「キャベツとか……?」というよくわからない返答をした。好きな食べ物を聞いて、食材を返される経験はあまりない。
「あんまり食べ物に興味がなくて……」
初対面との人の話題作りの鉄板は、こうして敗北するのだという気持ちを味わった。世界は広い。食に興味のない人も星の数ほど存在するという事実を、彼女はそのときまざまざと思い知った。話題を間違えたことを悟り、彼女が失敗の表情をしたのだろう。乙骨も慌てて言葉を重ねた。
「ああでも、どちらかというと人が食べているのを見るのが好きなので」
「はあ……」
「さんはすごくおいしそうに食べるので、見ているの、好きです」
臆面もなく言われて、返答にまた困ってしまった。俯いた彼女を見る乙骨の視線を、柔らかさを彼女は知らない。乙骨は湖の真ん中の辺りでボートを止めると、ふいっと空を仰いだ。少し顔を赤らめて俯いていた彼女も、同じように空を見上げる。空は晴天で、青が遠くまで突き抜けるようだった。
「僕はどうもあまり、自分の感情や感覚が鈍感な質みたいで」
「はあ」
「だから他人と一緒にいると、その人が感じたり感動したり。美味しいって顔とかいろんなものを見せてくれるから、だから僕は人と一緒にいることがすきなんです。
さんは、多分魂がすごく強くて、しなやかです。だからどこでも、どんな環境でも、自分の活路を見出せるんでしょうね。仕事が忙しいときでも、コンビニで買うものはいつも違うものを選んでいたし、魂の状態でも食事をして自己回復をしようとしていた。僕は生きる力が強いというのは、きっと今を楽しむ力だと思うので」
「……ありがとうございます?」
多忙だろうが幽霊状態だろうが食い意地が張っていたことを、美麗字句に変換して、褒められた気がする。釈然としない気持ちのまま、乙骨の横顔を見る。風が彼の白い額を撫でて、髪が揺れる。乙骨はその心地よさそうな顔のまま、ごろんと後ろへ倒れた。ボートが揺れて、体が揺れる。初めは驚いたが、船底へ寝ころんだ乙骨が少し笑っていたので、きっとそんなに構える必要はないんだ、と悟った。
乙骨を真似て反対向きに船底へ転がる。また少しボードが揺れた。視界はもう空しか見えなくなって、船底へ水がぶつかる音と、乙骨の呼吸音と、周囲の森の葉擦れの音だけが聞こえる。
腹の中の『棺那比』は確固とした形のまま、まだそこにいる。自分がもはや普通通りに死ねない体であることも、乙骨のいう術式というものが体に刻まれていることも、今ではありありとわかる。
不安がないわけではない。恐怖がないわけではない。けれど少なくともきっと乙骨は、彼女の味方でいてくれる。先ほどの話はきっとそういう意味なのだろう。空を眺めながら、風を聞きながら、彼女はそう思った。
きっと乙骨憂太は信頼できる人間で、だから彼が彼女が殺すときがもし来ても、いつかの自分は許すだろう。きっと喉を刃の前に差し出して、楽しい人生だったと笑えるだろう。
そのときに少しでも乙骨が悲しんでくれればいいな、と彼女はまどろみに沈みながら、思った。
「彼女、やっぱり呪力ないね」
その後彼女が乙骨に連れられて日本へ帰国して、いの一番に連れていかれたのは、呪術高等専門学校という学校だった。乙骨もこの学校の卒業生なのだと聞いた。そこに在籍している家入という女性は、彼女を隅から隅まで事細かに調べると、乙骨と同席した数名の呪術師に向かってそう説明した。
「全くではないけれど、外部へアウトプットできるレベルの自身の呪力はない。現在、外部へアウトプットされるほど漏れているこの呪力は、乙骨のものだね」
「けれど、乙骨の呪力は『棺那比』を封じるのに使用しているんじゃないのか?」
日下部と名乗ったスーツの術師が聞く。
「現在の『棺那比』が縄張りの土地を離れ、だいぶ弱っているということもあるけれど、それでも乙骨が流した呪力に対してのリターンが全く見合っていない。つまり彼女は、彼女の術式は、いわゆる増幅装置なのだと思う。
要は、元々反転術式を順転として出力する術師ではなく、順転でも反転でも自身に流された『基準値』となる呪力を増幅してアウトプットする。だから『リカ』の負エネルギーも体に馴染んだし、その際に『リカ』の核である構成要素『折本里香』が増幅して、暴走できてしまった」
彼女には家入の言っている内容はほぼ理解できなかったが、周りの反応からあまり他に例のないことであるのはわかった。仕事は乙骨に刺された翌日から休職扱いになっていたが、今更戻ることもできず、内部に抱えた『棺那比』ごと出身地へ、『棺那比』の鎮めていた土地へ戻る以外に、彼女に選択肢はほぼなかった。
倒れて入院しているという祖母は、『棺那比』が暴走したときの危篤状態から一命は取り留めたとのことだが、意識は戻っていない。意識が戻るか、そのまま息を引き取るかは、確率としては半々です、と病院で説明を受けた。
両親は、とくに母は彼女と祖母の特異な体質について、ぼんやりとは理解していたらしい。母には彼女と同じような性質はなく、しかし祖母から家系にそういう能力のあるものが生まれること、そしてその子どもはゆくゆくは『棺那比』の社の管理を行う必要がある。そういう話を母から聞いた。大学生の弟はずっと祖母の面倒を見ていたようで、瞼を赤く腫らしながら、帰ってきてくれてよかったと一言だけ言った。両親よりも祖母の病状よりも、弟のその泣き腫らした瞼に一番心を抉られた。
『棺那比』は祖母の家へ戻ってきてから、完全に力を取り戻した。それを押さえ込むのに内部で増幅させていた呪力だけでは足りず、ついてきていた乙骨に再度呪力を流してもらうことになった。
それからはひと月に数度、乙骨が様子を見にやって来て彼女へ呪力を流していく、という手筈になった。彼女も内部の『棺那比』が安定するまでは外部からの呪力が必要なことは肌で感じ取ったし、外から見ていても、『棺那比』の状況はある程度わかるようだ。『反転術式』というものを扱える人物、かつそれを他者へアウトプットできる人物はかなり限られており、乙骨はその数少ないうちの一人だ、ということだった。
「じゃあ、呪力流すので、顔を上げて」
彼女が理解できないのは、『棺那比』を初めて取り込んだときと同じように、乙骨が口移しで呪力をくれることだ。優秀な術師のため任務量も多く、多忙だという乙骨はそれでも都度都度、地方の祖母の家にやって来る。この家から通える範囲の仕事と、祖母がしていた和裁の細工物を作って納品する以外はだらだらと生活している彼女にとって、多忙の合間を縫ってやって来る乙骨を無碍にすることはできなかった。けれど、それでも、と思う。
今回もやってきて早々に、乙骨は彼女の腰を抱いて顔を上げるように言った。納得いかないまま、ちらりと顔を上げれば、その間に唇に吸い付かれる。ぐっと体を柔く押されて、上から齧りつくようにキスを、されている。
これはもう、口移しとかそういうものではなくて、普通にキスなんじゃ?
乙骨の舌がねっとりと彼女の唇の裾を伝い、薄く喘いだ端から舌を差し込まれる。粘膜と粘膜が擦れ合うと、脳髄が痺れるほど気持ちがよかった。腹の奥がじくじくと濡れていく。それに追い打ちをかけるように、乙骨の指が背筋や腰の輪郭をなぞってくる。
困ったことに、気持ちがよすぎてやめてくれと言い出せないのが、悪かった。はっ、と小さく吐いた息の間に、もう十分だ、と言おうとするのに、それを言う前に乙骨が再度吸い付いてくる。彼女の体からは力が抜けて、ほぼほぼ乙骨の手のひらに支えられているだけ、畳に倒れ込んでしまう一歩手前。そんな有様だった。
「あ、の……」
「ん?」
再度唇をすり合わせてくる乙骨の合間を何とか縫って、小さく声を上げる。どろどろに溶けたような目をした乙骨は、彼女の首筋や肩を先をなぞったまま、その声を受けた。
「反転術式って、口移ししかできないもの、ですか?」
「やっと気づいたんですか?」
彼女の問いに、乙骨は愚かな者を見る目で笑う。首筋をなぞっていた乙骨の指先が降りていく。頚骨を覆う首の肉の筋、鎖骨、胸骨、そして。
「僕がしたかったので」
実際乙骨は、彼女に反転術式をこれからも継続的に流さなければならない、となったとき、普通に手のひらや別の場所から供給するつもりでいた。口から口へのアウトプットは、やむを得ない緊急時故、行ったもののはずだった。
けれど実際に、『棺那比』の押さえ込みに呪力が足りないことを感知したとき、彼女は困惑し戸惑った表情をしてから、意を決したように目と口を閉じて、乙骨へ口を突き出した。耳が少し、赤かった。なのでマアそのまま、まんまと魔が差して、今に至る。据え膳はいただくタイプの男である。
しれっと言い切った乙骨に、彼女は口をはくはくとさせて、言葉が出ない。乙骨はそれをいいことに、力が抜けて支えられるのみだった彼女の背中を、支える手のひらを、緩めた。頭をぶつけるまでの距離はもうなかったが、それでも十分驚いたらしい彼女は、目を丸くして乙骨を見ている。
どうせもう、溶けている。
乙骨がぬっとりと唇を擦り合わせて服の合わせ目から腹を撫でると、彼女は、は、諦めたように目を閉じて乙骨の服の裾を握った。おずおずと触れて絡み合う指が、握り合った手のひらが、二人の証左だった。

死滅回游後、宿儺との決戦後にはいくらかの事後処理が多く、反比例して、関われるものの人数は多くはなかった。
乙骨は各地を飛び回りながら活性化した呪霊を祓い、人を助け、弔った。そうしているうちに、被害が異常に多い地域と少ない地域というものが見えてくる。次の仕事になぜ多かった、少なかったか、という理由の精査が入るのは、組織としては健全で、自分たちが失ったものが多いにせよ、まだ呪術界に生きる意欲があるからだと思えた。
今回尋ねた地域は『少ない』ほうの地域だった。恐らくその要因となったであろう老婦人は、窓や補助監督からの調査や聴取では自身が何を操っているのか、管理しているのか理解していなかった。ただ非常な稀有な特異体質である可能性がある、という報告が上がっていた。
出力される呪力が、反転術式を回していなくても『正』として出力されるというのだから、それは確かに珍しい。羂索に目を付けられたなかったのが奇跡のようなものだが、どうにも出力の大半は管理している呪霊を封じるための呪具に注いでおり、残った呪力は稼業の細工物に少量ずつ注いでしまう。見つからないためのデザインが偶然なのか、意図なのかは不明だが、合理的に洗練されたソツのなさだったのは事実だ。
乙骨は、そのときに担当していたある子どもの守りを強化できる呪具が必要だった。子どもは羂索の放った呪霊に取り憑かれたうちの一人で、魂との同化レベルが高く、祓うことは困難とみられた。そのため、常に反転術式で呪霊の呪力を中和し、子ども側の魂を保護する必要があった。
老婦人の作るちりめん細工や日本刺繍は、針で繕う際に呪力がこもるようで、大きくはないが正エネルギーを纏ったものとして有用だった。子どもの状態を家入に相談した際に紹介を受け、乙骨自身も老婦人の作るものを実際に見てみたくて訪れた次第だ。
老婦人は柔和であまり主張の激しくないタイプの人物で、高専や呪術関係者の灰汁の強さに食傷気味なのではないか、と勝手な危惧をしたが、乙骨にも親切に対応をしてくれた。彼女の作成した細工物から、目的とする子どもへの守りをするのに最適なレベルの呪力が込められたものを選ぶ。彼女の術式は一度の出力値が極小だが、時間経過で増幅する傾向がある。老婦人自身は呪力や術式というものを理解していなかったが、稼業として針で刺す工程を経る細工物を作ってきたということは、彼女の祖先は自分たちに刻まれた術式についての性質を、ある程度理解していたのだろう。乙骨自身も隔世遺伝や先祖返りの典型例のような存在のため、老婦人の困惑も状況も、多少の理解ができる。
老婦人の出してくれた細工物の中から子どもに取り憑いた呪霊との相性がよさそうなものを見繕い、条件に一致したものは見つかったが今後も世話になることが多そうだ。老婦人の作品をしげしげと眺めていると、それのうち、糸や布、刺繍の配置などのセンスが少し違うものを、少量だが見つけた。
「ああ、それは孫が作ったものです」
乙骨がそれらを不思議そうに見たのが分かったのだろう。老婦人が作品の中からいくつかを抜き出して並べる。
「あなたがたの言われる『呪力』というものがあの子にも少々備わっているようでして、社守の仕事をゆくゆくは継いでもらいたいという気持ちもありましたから、春先の休みの間、ここに住まわせていたんです。この辺りの細工は、その折に作ったものかしら」
「お孫さんも、同じような術式を……?」
「私にそういうものがあるとお言いなのであれば、私の目から見れば、あの子にもあるのでしょうね」
老婦人は言い、並べた細工物をじっと眺めた。老婦人は術式持ちとは言え年齢も年齢だ。これから先の人生で呪術やそれに付随するものと関わることも、少なくないだろうが人生のすべてが呪術にはならない。けれど彼女の孫については、きっとそうではないのだろう。
「乙骨さんと同じくらいの年頃じゃないかしら。もし会うことがあれば、どうぞよろしくお願い致します」
「あ、いえ、こちらこそ」
深々と頭を下げられ、乙骨も慌てて頭を下げる。老婦人は言葉少なにほほ笑んだ。彼女の孫が刺したのだという刺繍は老婦人の物と比べれば拙く、刺繍自体も込められた呪力もまばらだ。それでも一針ずつを丁寧に刺したことがわかること、込められた呪力が指先に馴染むこと、乙骨は老婦人が孫を心配する気持ちが少しだけだがわかる気がした。
担当している子ども用に老婦人のちりめん細工の根付と、彼女の孫が刺したという刺繍の布を譲り受けて乙骨は老婦人宅を辞した。孫の刺した刺繍を老婦人は拙いものだから、と渡すことを渋ったが、乙骨はなんとなく、その刺繍を気に入ってしまったのだ。鷺のような白くくちばしの長い鳥の横顔、少し間の抜けたその瞳。指先に馴染む呪力は温く、じんわりと沁みるように思えた。
老婦人の家を出て、駅までの道を歩き出す。季節は春で、少し向こうに満開が飽和したころの桜が咲き誇っていた。白い花弁が風にあおられて、散っていく。山の裾野を、その淡い白が染めていた。
少し向こうから、小走りで駆けてくる人影がある。
乙骨と同年代ほどの白い肌の女性は、頬を淡く染めて駆けてくる。散っていく桜を眺めながら走っていた彼女は、道の先に乙骨がいるとは思いもしなかったのだろう。乙骨の姿を認めると少し罰の悪そうな顔になり、小さく会釈して通りすぎてから、再度駆け出した。その横顔を、眼差しを、乙骨はまじまじと見ていた。
彼女が駆けていった先には、老婦人の家がある。乙骨は思いもかけず、思わず、振り返った。山の裾野を彩る桜が、ざやざやと彼女へ白い花弁を吹きかける。駆けて行った彼女は少し向こうで、「おばあちゃーん」と叫んだ。庭先で乙骨を見送っていた老婦人の姿を見つけたのだろう。
祖母を呼びながら、老婦人宅の敷地へ走っていく。乙骨はその姿が見えなくなるまで、眺めていた。そうして自分が自失していたことにやっと気づいて、ぼやぼやと歩き出した。
山の裾野から、白い花弁が吹きかかる。山色の着物の裾を彩る繊細な刺繍細工のような桜。それが散って、風が吹く。想起する。思い出す。白い花びらを孕んだ風は彼女の頬へ吹きかかり、風にあおられた髪を押さえて、あのとき彼女はまっすぐ射貫くように、乙骨を見た。
その眼差しの透明さを、真摯さを、鋭さを、うつくしさを。乙骨はどう形容すればいいかわからない。あの刺繍を刺した人と会いたいと思った。その人の眼差しがあまりにも心へ突き刺さり、鮮烈であった。
乙骨憂太はその日からその女の眼差しを忘れられず、有り体にいえば、恋をしていた。マア要するにいわゆるひとつの、ひとめぼれ、というやつだった。