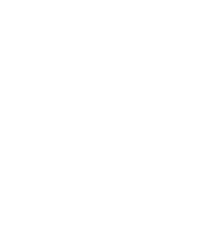空気の乾き方、湿度、重さ、肌に纏わりつくあの感じがない。そこが全く違うのだった。
ここで目覚めてもう数日になるが、朝目覚めるたびに彼女はそれを感じる。与えられた寝室のベッドは自室のそれよりも遙かに大きく、また頑丈で柔らかなマットレスを使用しているようだった。のそのそとシーツの中から起き上がり、部屋を出て右手にある洗面所へ向かう。同居人は今朝も既に炊事を始めたようで、がらんと吹き抜けの広いロッジの中には、階下の煮炊きの匂いが漂っている。くつくつ煮られるスープの匂いも、ぽつぽつと艶やかな香りとともに抽出されるコーヒーの匂いも、数日まではとても縁遠かったはずのものだ。彼女は洗面所で手早く顔を洗うと、買い揃えられた基礎化粧品を申し訳程度に塗り込み、階下へ降りた。
「ああ、おはようございます」
同居人は今朝も爽やかな笑顔を伴なって、彼女を振り向いた。もう少しでできるから待つように言って、マグへコーヒーを注いで渡してくる。彼女はそれを礼の形に小さく首を曲げてから受け取ると、がっしりとした木製の椅子の上に両膝を引き上げて、ちまちまと啜った。窓の外では白い日差しが雲間から差し込んで、木々の緑を弾くように光っている。その空の晴れ方と植わっている木々、そして傾斜のないだだっ広い平野は、何度見ても生まれてから四半世紀以上生活した日本の国ではないようだ。
同居人は今見ても機嫌や気分の上下の分かりにくいフラットな顔つきで、鉄製のフライパンから卵を掬ってプレートへ盛り付けている。じわじわと焼けるハムかベーコンかの油の匂いと、くつくつと煮える野菜のスープと、それを差し出す男の手を見比べて、彼女は幾度目かの嘆息をした。彼はそんな彼女を前髪の奥からじっと見て、その視線に彼女が気づいてからようやく、にへら、と笑ってみせる。
彼が、――乙骨憂太が差し出したカンパーニュに似たパンは硬く焼き上げられており、齧りついたら口の端が切れてしまった。鉄錆の味がした。

乾いた血の味がすると思うのは、疲労を抱えて戻る夜分、朝起きて今日も終わりのない日常を送るとき、そして日常の中で噛みしめた唇の端。
一般的にニュースで報道される類の、批難の声が上がるような各種のハラスメントが横行しているわけではなかったが、繁忙期と呼ばれる時期には帰宅するのが終電間近の電車になるような、そんな職場だった。無言で仕事を片付けて、今日もギリギリで電車に飛び乗れたことに安堵する。しかし、夜が明ければ今日と同じ日常を、あと一か月ほどは続けなければならない。
これが『永遠に』『終わりはわからない』と言われれば、それは電車が走り込んでくるホームへ飛び込む人間も存在するだろう。そういう心情を理解できてしまうようなことが、日常だった。
乙骨憂太はそういう彼女の日常の中に、ひそりと現れた。深夜の電車に乗って帰宅した際に、翌朝に食べるものと少し何か腹に入れる眠るため、コンビニ立ち寄る。乙骨という青年はそのコンビニで深夜にレジ打ちをしていた。
大きくて丸い瞼の形と、すらりとした鼻筋が真っ白でいかにも硬そうで、初めて見たときは綺麗な人だ、と呆けたことを覚えている。乙骨憂太は彼女自身と同年代の青年に見えたが、定職がないのかそれとも副業などの別の理由か。彼女が帰宅するような深夜帯のレジを担当しているようで、二週間もすれば、深夜に帰ってきてオッコツ青年(その頃は名札に表記されたカタカナでしか彼の名前を知りようがなかった)の麗しい 顔 を拝むのがひとつの習慣になっていた。
現金なもので、あんなにも深夜に帰宅するような生活が辛いと思っていたのに、終電までにはなんとしても帰ろうという気概が彼女にはできたし、実際そのために仕事をしていた。あまりに美しい青年の顔を拝みたかったこと、そして彼がコンビニに勤務しているそれ以外の時間帯を知りようがなかったこと、その二つが理由だ。その時期の彼女にとっての癒しのひとつは間違いなく、『オッコツ青年』の顔を見ることだった。
数週間後には、オッコツ青年は疲労した顔で帰宅する彼女を見て「お疲れ様です」と当たり障りのない挨拶をするようになったし、彼女も身構えることなく「ありがとうございます」と礼を言うようになった。
「やあ、今日は気温が高いですね」
「すごい雨ですね、濡れませんでしたか」
「足元に気を付けて、滑りやすくなっているので」
「今日も遅い時間ですね」
「すごい顔色ですよ、寝ていますか?」
不思議なことに、彼女が帰宅時コンビニによる時間に他の客がいたことは多くなく、店内にはいつもオッコツ青年と彼女のみだった。深夜の日付が変わったような時間だったのでそういうものかと思ってはいたが、都合がよすぎた。オッコツ青年が彼女を気遣うような言葉を口にしたときにも、あまりに都合よく周囲に他人がいなかったので、彼女は思わず涙を溢してしまった。
「あ、…れ。すみません、なんか涙出てきた」
「うわ、大丈夫ですか、ハンカチあったかな……」
「いえ、ず、すみません、お構いなく」
慌てて鼻を啜って手の甲で目尻を拭うと、滲じみ切った化粧のアイラインとラメが手の甲に移った。オッコツ青年がレジ内から出してきた備品のティッシュをありがたく借りて、目端を押さえる。彼はなんでもないことのようにレジ会計を進めて、袋へ商品を詰めた。コンビニでオッコツ青年を見かけるようになって数週間経つが、いまだに拙い手つきだった。
「やっぱり仕事が大変なんですか?」
「そうですね、でも、あと少しで繁忙期も終わるので。それが終われば」
「でも、今のあなたが辛そうだ」
レジに表示された会計を電子決済で終わらせて、礼を言ってティッシュの箱を押し返す。涙と化粧を拭ったティッシュは、服のポケットへねじ込んだ。
オッコツ青年が差し出すレジの袋を受け取るとき、ふと、オッコツ青年が彼女の手を掴んだ。慌てて引っ込めようとするが、それよりも強い力でオッコツ青年は手を掴んでいる。困惑して彼を見れば、オッコツ青年は少しだけ身を乗り出して彼女を見ていた。
「これ以上の限界が来る前に、環境を変えることをお勧めします。僕も相談に乗りますから」
「あの……」
「軽い気遣いの言葉だけでそんな風に泣くなんて、通常の精神状態ではない。もっと自覚すべきです」
オッコツ青年の手のひらは顔つきの柔和さとは違って皮膚が厚く、胼胝のようなものもあった。見た目とは裏腹のごつさ、硬さに彼女はどきまぎとして、慌てて腕を引く。
オッコツ青年はそれ以上は抵抗することなく、彼女の手を離した。慌ててレジ袋を掴んで、お辞儀をして走って帰る。帰宅したときには息が切れていて、ぜいぜいと自分の呼吸ばかりが耳に障った。折角購入したコンビニの惣菜は食べることなく、彼女はそのまま眠りについた。
その翌日に「今日はコンビニに寄らずに帰ろう」と思ったのはオッコツ青年に会いづらかったわけではなく、自宅の冷蔵庫に前日に食べられなかった惣菜がまだ入っていたからだ。
コンビニに寄らずに帰るのにそこの前を通るのも気まずい気がして、普段は使わないほうの道を通った。コンビニ前を通って帰宅していたのは、大きな道に面しているため人通りがあるのと、街灯が多いからだったが、こちらの道はやはり人通りも街灯も少ない。
彼女はポケットの中のスマホの存在を確認し、足早に歩いた。それに気づいたのは、小さな児童公園の近くだ。
視界の端に映った黒い靄のようなものが、捉えようとするとさっと消える。ばくばくと心臓が鳴る音が聞こえた。
ぎゅっと鞄の持ち手を握ると、アスファルトを蹴って駆け出した。かつかつと自分のヒールの音と、後ろからギチ、ギチ、と何かが擦れるような歯噛みするような音が聞こえる。
こういう類のものに追いかけられるのは初めてではなかった。子どもの頃にはよくあったが、あれは子どもの妄想や夢だとばかり、思っていた。
は、はっと自分の吐き出す息の音が煩い。児童公園の中を走り抜けようとしたが、すぐ耳の後ろで「く、ちち」とそれが笑う声がした。笑い声だと思ったのは、それが楽し気に聞こえたからだ。驚きと恐怖に足がもつれて、地面に倒れ込む。
それには、夥しい腕が生えていた。
それは異形だった。
それには、頭蓋の右横まで裂けるような大きな口があった。
それは笑っていた。
それには、後光のように背負う金冠があった。
それはほのかに光っていた。
ぞ、らり、と聞き覚えのない音がする。それが生やした無数の腕を、彼女へ差し出した音だった。形は確かに異形であるのに、ひとつひとつは驚くほどたおやかで美しい指先だ。それの指先が伸びて伸びて伸びて、鼻先、目の前。それの眼窩のあるだろう場所を見れば、右にだけ裂けた口の端が持ち上がり、にんまりと笑って見えた。
はく、と息のみ、喉から絞り取られる音がする。悲鳴は、出なかった。
しかし、最初に感じたのは風で、彼女の隣を駆け抜けた。一拍おいてザシュだとかドシュだとか、何かを断つ刃の音がする。
視界に映ったのは、いつものオッコツ青年の後ろ姿だった。無数に生えたそれの腕の数本が彼の持った刀に切られ、地面に落ちる。彼はそれの前に立ちはだかり、まだ腕を伸ばそうとしたそれの腕の数本を再度切りつけ、千切りとった。それが声にならない断末魔を上げてずるりと後ろに下がる。
そのままそれが闇に溶けて見えなくなるのを見送ると、オッコツ青年はこちらを振り向いた。
「やあ、昨日ぶりですね」
「あ、え」
「今日はコンビニに来てくださらなかったので、どうしたのかと思っていました」
「あ、あなた…、……」
「ん。なんです?」
「あなた……、な、なに?」
飛び出た声は誰何の声ではなく、モノとしての定義の問いだった。彼にもそれは伝わったのだろう。眼差しをすうっと細め、一歩、こちらへ歩き出す。傍らに持った刀の刃がぬらりと光った。
「申し訳ないが、僕の見込みが甘かったようだ」
彼がそれを振り上げて構えたのは、どうにも必然に思えた。
どうして疑問に思わなかったのだろう。この美しい青年がなぜ自分のような取柄も何もない女に優しく話しかけたのか。きっと、何か他に目的があったからだ。
私のようなどうでもいい、なんでもいい人間に、彼のように美しく親切で救いのような人が現れるはずなど、なかったのだ。
「痛くはないでしょう、一瞬で終わらせますから」
オッコツ青年はそう言い、振り上げた刀を振り下ろす。ひゅう、と刃が風を切る音がした。目尻から一滴だけ、涙が流れた。つるりと流れて、浚われて、なかったかのように消えた。

朝食を終えると、彼は洗濯と掃除をすると言って彼女をリビングダイニングから追い出した。自分も手伝うと小声で言っては見たが、今日も乙骨の有無を言わせぬ笑みに黙殺されて、しおしおと自室として与えられた階上の部屋に戻る。
朝食を食べ終えて体は温かく、何もすることがないと言うのであれば眠気が襲ってくるのは自然なことだった。ベッドに座ってからは転がるように眠りに落ちた。階下では乙骨が掃除か何かをしている雑音が、ことこと聞こえてくる。
眠っているときに他人が生活音を出すなんて実家にいた頃以来で、ああそういえば、実家の両親や祖母はどうしているだろうか、とぼんやり思った。
目が覚めたときには階下からの生活音は聞こえなくなっており、しんとしていた。ベッドから起き上がり時計を見れば、午後十一時を指している。階下にも乙骨の姿はなく、彼女はぐるりと回りを見渡してから外に出てみることにした。
ここで目を覚ました初日に少しだけ外の様子を見せてもらったが、一人で野外に出るのは初めてだった。ここはどこなのか?という彼女の問いに、乙骨は笑うだけで答えてくれなかったが、やはり野外の景色を見ればここが日本でないことは、確かなのだった。
寝起きしている赤っぽい外壁の住宅は、いかにも北欧だとかそういう雰囲気を持っている。室内の居心地が異常のよいのも、昔に何かで見たその地方の暮らしに沿っているように思うので、恐らくここは北欧と呼ばれる国の内のどこかではないか、と思うのだが、これだと思える証左は今のところ見つけられていない。住宅を出てすぐの舗装さていない小道を歩き、少しすれば湖が見えてくる。見渡す限りが平野で、日本では視界の端のどこかに山脈があったのだということを再度実感した。
湖が見える位置で立ち止まり、木の根元に腰を下ろす。瞬くように天気が良いので、湖から吹き抜けてくる風もからりとして気持ちがよかった。少しだけ肌寒かったな、と後悔しながら、ぼんやりと湖を見つめる。
乙骨――乙骨憂太と名乗った彼は、非常にまめまめしい人だ、というのが彼女の評だ。リビングで座り込んでぼんやりとしていれば、彼は温かいコーヒーだとか紅茶だとか、暇つぶしの本だとかラジオだとか、果ては昼寝用のブランケットまで持ってくる始末で、実家でもこんなに手厚くもてなされたり構われたりした覚えはない。彼女はいつもぼんやりとそれを受け取り、乙骨の曖昧な笑みを見る。
どうも、どうすればいいかわからないとき、彼は微笑むという癖があるようだった。彼女がどうして自分はここにいるのか、と聞くときも、同じような笑みを浮かべた。
少し風が冷たく感じてきたので、立ち上がって来た道を戻る。住宅の前には黒っぽい車が一台と、少しだけ慌てた様子の乙骨の姿が見えた。どうやらいないと思ったのは、買い物に出ていたらしい。
「ああ、どこに行ったのかと……」
「すみません、湖の方へ行っていました」
書置きでも残したらよかったですね、と言えば、乙骨は少し腑に落ちないような微妙な顔をした。その後「是非そうしてください」と朗らかに言ったが、彼にはそういうところがある。どういうタイミングなのか、ごく一般的な会話で「腑に落ちない」「虚をつかれた」「憮然」というような表情をするので、他人との関わりの希薄な人だったのだろうか、と勝手な推測をしている。
買い物したときに焼き菓子を買ったので、お茶にしませんかと言われて屋内に入る。合わせて、寒かっただろうからと薄手のブランケットを渡されてソファへ座り込めば、確かに水辺は肌寒かったのだろう。ブランケットと日の差す屋内の温もりがじんわりと体に染みた。乙骨が差し出したお茶はシナモンティー、購入したという焼き菓子は、生地にドライフルーツを混ぜ込んだパウンドケーキだった。
洋酒の香りのする菓子を齧り、お茶を啜っている自分を乙骨は向かいの席から眺めている。目があったのに彼は微動だにせずこちらの目を見つめ返してくるので、結局居心地が悪くなって目線を逸らしたのは彼女のほうだった。

刃の冷たさを感じたのはほぼ一瞬で、次の一瞬に感じたのは強烈な熱さだった。これは「痛い」という感覚だ、ということが追いついてくる前に袈裟懸けに切られた傷と重ねるように、オッコツ青年は刃先で喉の柔いところを突いた。研がれた刃が公園の街灯の光を受けて、煌めく。我慢するとかしないとかそういう問題ではなく、息をするようにごぼりと血が口の中から溢れてきた。
彼の顔を見る。オッコツ青年は怒りでも憎しみでも、悲しさでも悔しさでも憐憫でも、何でもない表情をしていた。それはきっと、無であった。
「ど、…して」
喉から零れたのは疑問だけでそのとき始めて彼は、眉を顰めた。ずるり、と彼の背後の暗闇から何か大きなものが這い出る。「ゆーた」 小さくか細く名を呼ぶ声は、幼い子どものようであった。
その記憶は、そこでぶつりと途切れる。
目が覚めたのは、柔らかく心地のいいソファの上だった。ぼんやりしていた意識が急に浮上するような、まどろみの中から覚醒するような心地。急速に周囲への知覚がはっきりとし、顔を上げればオッコツ青年が目の前に座ってこちらを見ていた。
どうして彼がこちらを見ているのかも判然とせず、ただコンビニに寄らなかったこと、自宅の冷蔵庫の中の昨晩購入した総菜を食べられなかったことだけ思い出された。くう、と腹が鳴るような心地がした。冷蔵庫の中身についての記憶を思い出したのは、自分が空腹だったからなのだろう。
「……お腹が空いた」
ぽつりと溢すと、こちらをじっと見つめていたオッコツ青年は目を丸くした。今思えばあんな状況での第一声が空腹を訴えることなのだから、我ながら食い意地が張っている。
「……お腹が空いたんですか? 本当に?」
「え、はい。なんか、すみません」
「あ、いえ……」
オッコツ青年が向かいの椅子から立ち上がりながら小さく「すごいな」と呟いたので、ますます恥ずかしくなる。彼女は羞恥に体を縮こまらせた。そんな彼女を見て、オッコツ青年は慌てた様子で首を振る。
「いえ、そういう意味ではないんです。何か用意するから、少し待ってもらえますか」
「はあ、」
「何か嫌いなものや、食べれられないものは、ああ。いや、その前に」
オッコツ青年は何かを思い出したように言って、彼女の前で膝を折った。ソファの上で膝を抱える彼女を下から覗き込んで、にっこりと笑う。その瞬間に深夜のあの公園での血の匂いが脳裏へフラッシュバックしたのに、彼はあまりに何事もなく笑う。だから、彼女は何も言うことができなくなってしまった。
「僕は乙骨――乙骨憂太です。どうぞよろしく、さん」
乙骨のその笑顔は深夜のコンビニで見ていた、彼女が数週間癒しだと思っていたもの、そのままだった。どうしてそんな風に笑えるのだろう、あの深夜の公園で彼は彼女を刀で切り付けたのに。けれど「どうして」という問いは形になることはなかった。
乙骨は笑んだまま立ち上がって、キッチンへ向かっていく。その後ろ姿を見ながら、どうしてだろう、どこだろうと思う。不思議とあの深夜の公園での出来事を夢だと断じることはなかった。
彼は彼女を殺したのだ、血潮を浴びて笑ったのだ。
彼女は間違いなく、乙骨憂太に殺された。
そして今、ここにいる。