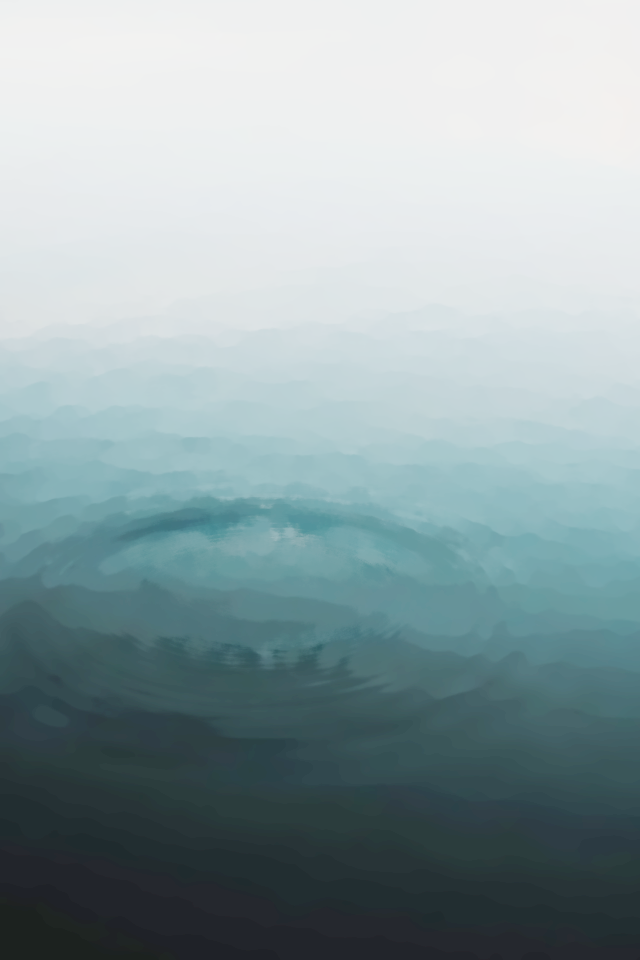 Where does she go?
Where does she go?
What does he do?
Will the merman team with Davy Jones,
And trap her at the bottom of the sea?
1
別れた男とホテルで再会するほど滑稽なことはない。知り合って何度目かのデートで、階下の部屋へ誘われた。ためしてもいいかと思えるほどには好感があったので、楚々と俯いた。否定をしなかった。はにかむような表情を作りながらお手洗いだけ、と言って席を立ち、ふと近くの席に見覚えのある長身を見つけてしまった。
わたしの昔からの些細な特技はよく似た双子の見分けが得意だったことで、今はそれを恨む。厚めの筋肉がついたその背中は、たしかにジェイド・リーチ。その人のものだった。あっと思う間に、その長身がこちらを振り向く。ちかり、とピアスの鱗が照明を反射して、光る。彼は一度だけ目を見開いたあと、にんまりと笑ってみせた。隣には同じく長身の麗しい美女がいた。
わたしとジェイド・リーチが付き合っていたのは、今は遠く、ナイトレイブンカレッジでの学生時代だ。TWLでの社会常識を身に着けるためという名目で、学園長はわたしをモストロ・ラウンジのアルバイトへ放り込んだ。アズールがにやにやと笑っていたので、それ以外の理由や取引があったのだと思うが、わたしは知らない。ただモストロの従業員たちは存外に親切に、丁寧に、根気よく、いささかの横暴を持って、わたしへTWLの礼節やマナー、淑女としての作法を叩き込んでくれた。その中の一人にジェイドもいたのが契機だった。
ジェイド・リーチという先輩は、わたしの周りにあまりいなかったタイプの男だったのも理由のひとつだった。見た目も言動も割と穏やかで真面目らしく見えるくせ、内実はまったく伴っていない。
一度モストロのシフトが入っていたのに勝手に山へ出かけてしまったことがあって、アズールがジェイドへカンカンと怒っている場面に出くわした。彼はしゅんと怒られているように見せて、アズールが目を離した隙にわたしに向かってにやりと笑って見せた。反省なんてしていないし、この人は穏やかさも真面目に見せるような言動も、そうしたいからしているだけなのだ。そう悟ったときに、存外面白い人だなと思ったことを覚えている。
幸か不幸かナイトレイブンカレッジの中に女生徒はわたし一人きりで、異世界人という物珍しさも相まったのだろう。ジェイドのほうもわたしに多少の興味を持ったようで、男女の付き合いをするようになるのに、そんなに多くの時間はかからなかった。
彼はそこそこにいい恋人であったが、NRC卒業後しばらくしてから別れた。理由はいわゆる、価値観の不一致というもので、別れ際には今では考えられないような修羅場であったため、つまり彼は、会いたい相手ではなかった。
わたしがお手洗いから戻るのを見計らうかのように、ジェイドは長身の美女を連れてバーを後にした。これ見よがしに階下の部屋のキーを持っていたので、彼らの目的も変わらないのであろう。別に今更気になることでもない。わたしはことさら澄ました顔をして、ジェイドのことを無視した。ジェイドは今からあの長身の美女を抱くし、わたしはこの隣の優男に抱かれる。もうこのホテルは使えないなと思いながらバーから出れば、随分先に出たはずのジェイドと先ほどの長身美女と、エレベーターホールで鉢合わせをしてしまった。
二人は随分と情熱的なキスとしており、ぎくりと足を止めればわたしをエスコートしていた隣の男も困ったように足を止める。ボーイを呼んで追い払ってもらおうかと思った瞬間に、腰をかがめてキスに耽っていたジェイドがこちらをちらりと見て目端で笑ったので、かちんと来た。隣の男のタイを引き寄せ、その唇へ吸い付く。男は戸惑ったようだったが、服越しに浮き出た腰骨を指先で数度たどれば、大人しく応えるようになった。
そこで苛立たしげになったのはジェイドのほうで、わたしが掴んだタイを離してそちらを見れば、ぎりぎりと歯を食いしばるような顔をしている。少し溜飲が下がったのでわたしはにこやかに笑い、隣の男を誘ってエレベーターホールを横切ろうとした。そのとき。
「ヘイ、ミスター。ハンカチを落とされましたよ」
ジェイドが声をあげた。いつの間に手にしたのか、確かに先ほどまで隣の男が胸元にしていたチーフがジェイドの手の中にある。ジェイドはにこやかにこちらへ近づいてくると、チーフを男の手のひらへ落とし、目を覗き込んだ。
「いい夜ですね。これからあなたも隣のアバズレと夜を過ごすので?」
「……何を言うんだ、急に。ハンカチを拾ってくれたのはいいが、彼女にそんな口を……」
「心配しないで、僕の目を見て」
齧りとる歯≪ショック・ザ・ハート≫と、彼が口の中でちいさく唱えるのを、わたしは止めることができなかった。ジェイドはひどく楽しそうに唇を歪めて男を見る。
「ねえ、その女を抱きたいんでしょう?」
「そうさ、大した女じゃないくせにずいぶんと勿体付けられた。今日こそ物にしてやるつもりなんだ。邪魔しないでくれ。
それとも? そっちの美女を譲ってくれるっていうのなら、また話は別だが」
男は、はっとして口許を抑えたが、もう遅い。ジェイドは学生時代のように鋭い歯を見せて笑い、彼が連れていた長身美女は呆れたように溜息を落とす。わたしをエスコートしていた男はみるみるうちに青ざめていった。自身が決して話してはいけない『本心』を喋ってしまったためだ。わたしも溜息を落とすと、長身美女と目が合った。呼吸を合わせ、目の前の男のタイをむんずと掴む。視界の端で長身美女が同じようにジェイドの首元を掴んだのが見えた。響いた破裂音は、二つだった。
2
「まじでドン引きだわあ」
先日の顛末を話して聞かせると、そんな気の抜けた反応をしてみせたのはエースだ。平日の昼過ぎのカフェは人気が多すぎも、少なすぎもしない。ほどほどに騒がしい喧噪の中は、そういった至極くだらない話をするにはうってつけだった。
「エ、別れて何年?」
「卒業してからだから、もうすぐ八年? 九年? 覚えてないですね」
「なのにお前からジェイド先輩の名前をつどつど聞く気がするわ……。怖ェえー」
エースが大げさに二の腕をこすってみせる。エースの言う通り、別れてそこそこの年月が経つのに、思い出すようにどこかしらでジェイドとは顔を合わせる羽目になるのだ。ここ二年ほどは出くわしていなかったので安心していた矢先の出来事が先日の騒動だった。あの後わたしは長身美女と二人で飲みなおしに行くことになり、友人が一人増えたのはまあいい。問題はああやって出くわすたびに当て擦りのようなことをし続けるジェイド・リーチ。その人だ。
「普通に考えればジェイド先輩の側にまだ未練があるんだろうけどさ」
「でも振ったのは向こうですよ。それにこの間はわたしのことを『アバズレ』って呼んだので」
「…………。ないわー引くわー」
エースはたっぷりと沈黙した後に、再度同じセリフを繰り返した。瞳には呆れの色が浮かんでいる。わたしも呆れている。ジェイドがすることは、まるでティーンの子どものようだ。別れるときだってもう少しまともだった。…いや、まともではなかったかもしれない。ジェイドは自分の主張を一切曲げなかったし、それはわたしも同じだった。お互いがお互いの主張を曲げなかったがために随分な言い合いになったし、お互いを詰る羽目になった。あまり思い出したくない。
「あんなにも言い合って別れてたのに、まだわたしに構ってくるその神経がわからないんですよ」
「んー、まア。でもさ、お前だって無視しないじゃん、やり返すじゃん。似た者同士だろ」
「……最ッ悪。次あったら絶対無視します」
「やば、藪蛇」
エースはわたしのしかめっ面ににへらと笑ってみせると、スマホを取り上げて時間を見た。戻りの電車の時間が近いのだろう。彼がたまたま仕事の取材でこちらのほうへ出てくると聞いて、カフェで待ち合わせたのだ。今日は愚痴を聞いてくれてありがとうと言えば、昔と同じように意地悪げな笑みを浮かべてから「面白かったしイーヨ」と素直に笑った。
エースと手を振って別れて、少し暗くなり始めた歩道を歩く。NRCを卒業してから住み始めたこの街はそこそこ栄えた商業都市で、ホテルもオフィスもレストランも商業施設もわんさかとある。近くのスーパーに寄って夕食の買い物をしたら、日は完全に暮れてしまった。さっさと帰ろうと目抜き通りをぶらぶらと歩いていれば、少し先に先ほどの話にも出ていた長身の背中を見つけた。今一番会いたくない男である。
回り道をしようか、と踵を返した瞬間にジェイドの近くにいた女が手のひらを振りかぶるのが見えた。追って、パシンと軽快な音が響いてくる。先日の長身美女とはまた別の女性なので、お盛んなことだと思って見ていれば、ジェイドを打った女性が言い捨てた内容が聞こえてきた。
「山だとか兄弟だとか、思ったよりも子どもっぽいのね。わたしはわたしを一番にしてほしいって言ったでしょう。残念だわ」
女はそう言いつのると近くで待たせていたタクシーに乗り込んで、どこかへ去っていった。残されたのは周囲の視線を集めるジェイドだけだ。ジェイドは数秒立ち止まってから、やれやれと髪をかき上げる。彼は言われた内容など気にも留めていないだろうが、そうでなく別なのは、わたしのほうだった。
「わたしは、ジェイドがアズールやフロイドを大切にしているところも、山の話をするときは目がいきいきするところも。好きでしたよ」
思わず近寄ってそう言えば、振り向いたジェイドはすこしだけ驚いたように目を見開いた。わたしとここで会うなんて思ってもみなかったのだろう。髪をかき上げたせいでセットは少し崩れて、ぶたれた頬はほんのり赤い。せっかくの怜悧な雰囲気が台無しだが、それはそれで色気があると思う女性も多いだろう。
「あなたが僕を褒めるなんて、何年ぶりでしょうか」
「別に褒めたわけではありません」
「ふふ」
聞いてはいない素振りで、ジェイドはわたしが持っていた買い物袋を勝手に取り上げる。ちょっと、と声を荒げればジェイドはこちらへ目線を流して見せた。
「お礼に夕食を作りましょう」
「結構です」
「お住まいは以前と変わられていませんか?」
「結構ですってば」
そう言いながらも結局、自宅までの道のりを長身と歩く。なんだかんだ、わたしはこの男が憎いが、それでも嫌って別れたわけではないのだ。それをこういうときにこそ、痛感させられる。その日の夕食は、久しぶりにジェイドの作ったアクアパッツアを食べた。相変わらずわたし好みの味で、美味しかった。それはもう、憎らしいほどに。
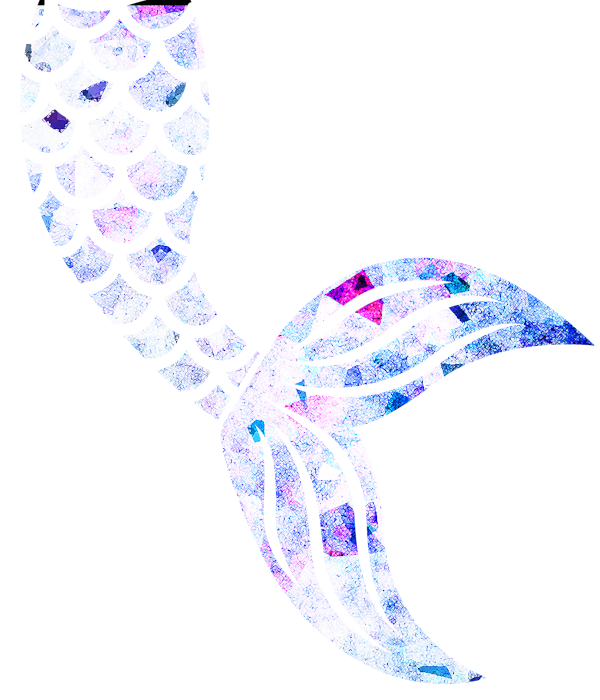
物静かな雨の日ほど感傷を誘うものはない。オンボロ寮の窓辺でぼんやりと庭先の様子を眺めていると、雨に塗れて長身の影が見えた。傘もささず、濡れるのを楽しむかのように歩いてくる姿はこのTWLでも少ない。きっと、元の世界ではもっと珍しいだろう。ジェイドは物腰の割に子どもっぽいところのある男だった。例えば電車の先頭で運転手を眺めて動かない幼子、ああいった無邪気さと頑迷さとひたむきさを感じる。
ジェイドは窓辺で自分を眺めているわたしの姿を認めると、閃くように笑った。ぐっしょりと濡れたダブルのタキシードは重たそうだったが、そんなことはおくびにも出さず、長い脚で水たまりを跳ね上げる。わたしは少し笑ってから、大きめのタオルと取りにバスルームへ向かった。
わたしとジェイドがうまくいくわけないなんて、きっと大人だったらわかり切っていた。わたしはどうしても元の世界に戻りたいと思っていたし、ジェイドは生家の稼業を継ぐのにふさわしい伴侶を必要としていた。恋人という関係だけなら、きっとよかったのだ。
「いつも思うのですが、雨ってどうして美味しくないんでしょうね」
「わたしの元いた世界の話ですが、空気中の塵を落としながら振ってくるから汚いらしいですよ。お腹……、はジェイドなら壊しませんね」
「もう少し心配していただけると嬉しいのですが」
「でも、普段から毒キノコもどきをよく食べていますし」
渡したバスタオルから顔を覗かせたジェイドは、ますます子ども染みた顔で笑っている。本当は彼は魔法の一振りでこの水気をすべて拭い去ることができるのだけど、いつだったか濡れた彼にこうしてバスタオルを渡したことが随分お気に召したようで、それ以来彼は魔法で水気を拭うことをあまりしない。ぐっしょりと濡れた彼をそのままバスルームへ押し込めて、一緒に入りませんかという軽口に「馬鹿じゃないんですか」と言い返す。
ずっといっしょにいたいなんて、バカげた、子ども染みた。そんなことを考えたのがすべての間違いの始まりだった。そうなることは周りの大人はわかっていたんだろう。
あのとき言っていた、幼い軽口の掛け合いをずっと繰り返していたかった。彼となら、どんな状況になってもその応酬を続けられるんじゃないか、そんな期待があった。あわい脆い、幼い期待。
恋を失うことがいい人生経験だなんて、とんだ欺瞞だと今でも思う。少なくとも、わたしにとってはそんなもの初めからこの世に存在しなければいいと思うほど、痛みと伴い、辛く、恐ろしく、後を引く苦しみであり、憎しみであった。心の柔らかい部分をジェイド・リーチという男に抉り取られて、それが身を切るように辛かった。あんなに他人を憎むことは、きっともうないだろう。
3
困ったなと思うのは、先日のジェイドがいい加減な挑発をした男は、数回一緒に仕事をした取引先の人間だったことだ。今も全く取引がないわけではなく、数か月に一度は運が悪ければ職場で出くわしてしまう。そして出くわすたびにあの日の弁明とジェイドについて問い質されることが些末だが、ストレスだった。
その日もたまたまあの男とオフィスのロビーで出くわしてしまい、休憩時間だったことも相まって彼が後ろをついて歩いてくる。別に彼が自分に対して紳士的でない思いを抱いていたことがあろうと、それをわざわざ暴いたのはジェイドだ。それに対して怒りを覚えるわけではないが、『それ』を知った上で仲良くしたくはない。この男はどういう気持ちでまだ自分に対して言い寄ってくるのか訝しみながら、適当にいなすことを繰り返していた。
ただ男のほうはいい加減に焦れていたようで、昼食を買いに出たときは周りの目もあって早々に退散していた。しかしその日の残業後、遅めの時間にオフィスを出ればそこにはまたあの男がいた。
「そうして待っていていただいても、お話することはわたしにはありません」
いい加減にうんざりとしてそう言えば、その男は、ならばせめてジェイドについて教えろと言ってきた。そうやって言ってくる相手に、どうして教えられると思うのだろう。わたしが思っていたよりもこの男はきっと馬鹿だったのだと今更ながらに悟る。下手に関係を持たなくてよかったのはジェイドに感謝するべきかもしれないが、そもそもこじらせたのはジェイドが原因だ。もういっそジェイドの連絡先を教えて押し付けてしまおうか。彼なら難なく交わしてくれるだろう。
すこし溜息を落としてジェイドの連絡先を端末から引っ張り出して連絡を試みていると、その様子を見ていた男がじりじりとした目でこちらを見た。
「お前はやっぱり、あの男と出来ていたんだろう。俺はとんだとばっちりだ。あんな風に恥をかかされて」
それは、確かにその通りだ。わたしとジェイドは付き合っていたし、ジェイドはわたしへの当てつけであんな適当な煽りをしたのかもしれない。あんな風に自分のユニーク魔法を使い潰すなんて、ジェイドらしくないことだった。わたしは目の前の彼に対して、少しだけ罪悪感を抱いてしまった。
「確かに申し訳なかったです。わたしは彼とはもう何の関わりもありませんが、多分彼があんなことをしたのは恐らくわたしがいたからなので」
「そうだよなア、そうなんだよなあ」
男が大仰に頷く。その表情に嫌なものを感じて慌ててスマホの通話ボタンをタップしようとしたが、それよりも早く男の手がわたしの手首をつかんだ。
「取引先の人間だから社会性を失うような手段には出ないと思っていたか? そうだな、しかし、ばれなければいいと思わないか?
性犯罪の大半は顔見知りによる犯行だっていうだろ? ・クロウリー」
男の腕がわたしの手首をぐっと捩じり、取り落としたスマホを反対の手でキャッチする。まだ付近には多少の人影はあるはずだ。大声を出そうと息を吸い込んだ瞬間に、みぞおちにそのスマホを叩きこまれた。大して魔力のない人間だと思っていたが、やはりわたしには魔力の感知はできないらしい。ちらりと見えた彼の左耳のイヤーカフには大振りの魔法石が埋め込まれていた。人体強化をしたのだろう。
「あの男はお前を餌にしたら来るんだろう。しばらく寝ていろ」
男が言って視界が滲んでいく。腹部の痛みとおそらく催眠の魔法もかけられたのだろう。じわじわと薄くなっていく視界になつかしさを覚えた。
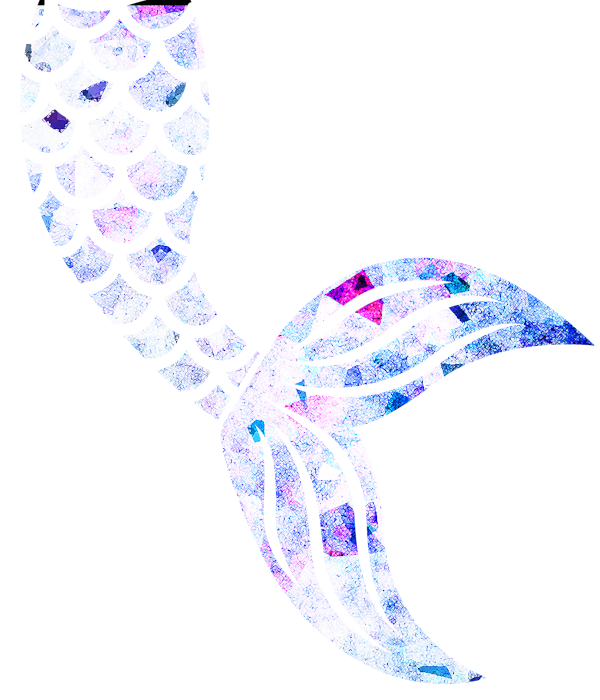
NRCなんてところはある意味で無法地帯だった。年頃の男子が多く集まればそういった部分も出てきやすいのだろう。わたしはNRC内で唯一の女生徒だったが、同時に一番の弱者でもあった。クロウリーは、学園長はわたしが女であることを公表するか最後まで迷ったようだが、結局おおやけとすることで逆にわたしを守ることにしたようだ。
隠すことと隠さないことと、どちらがよかったのかは今でもわからない。モストロ・ラウンジでアルバイトだけをしているときはまだしも、ジェイドと親しくするようになってからはさらに身体的に危険な目に合うことが多くなった。ジェイドがこうやってあちこちで恨まれてくるからだ。わたしもどうにも、いつも何時もジェイドの弱みとして受け取られるようだった。
実際、わたしに危害を加えようとすれば確かにジェイドは現れたし、わたしを盾にすれば数度は大人しく殴られていたようだったので、効果はあると言えばあるのだろう。ただジェイドもアズールも、それを出汁にして相手を数倍に叩いて返すのだ。
つまりわたしが害されるというのは、ジェイドにとってもアズールにとっても、相手を潰す体のいい理由だった。
あの時もそうだった。わたしとジェイドが付き合い始めたときも、ジェイドかフロイドにボコボコにされた他寮生がなぜか知らないけれどわたしを攫って、ジェイドを呼びだした。呼び出したはいいけれど、再度数倍にボコボコにされた挙句、内容を知りたくもない、よからぬ書面に血判を捺印させられたいた。
ただジェイドの頬には珍しく傷があった。相手が放った魔法が近くの樹木にぶつかり、折れた木の枝が刺さりそうになったのだ。幸いジェイドが避けたので切れたのは表皮一枚のようだったが、それでも血が流れていたし、痕になりそうな深さだった。
わたしは腹が立っていた。ジェイドたちがそうして、『理になること』をわざわざ起こして回っていることに。それにいちいち巻き込まれるのにもうんざりしていたし、ジェイドがその度にわたしを助けに来て相手に殴られてみせることも嫌だった。わたしの知らないところでやってくれ。そう思っていた。
「いい加減にしてもらえませんか」
腹に据えかねて、彼の頬をハンカチで抑えながら、憮然と言った。ジェイドは眉尻を下げてみせ、いかにも困った顔をしてみせる。そういった顔をしてみせればいいと、そう学習しているのだろう。わたしはいらいらとして、彼の手にハンカチを押し付けた。背を向けて歩き出すと、後ろからジェイドがわたしを呼ぶ。最初は監督生さん、と呼んでいた。それがいつの間にか、、と呼ぶように変わっていた。
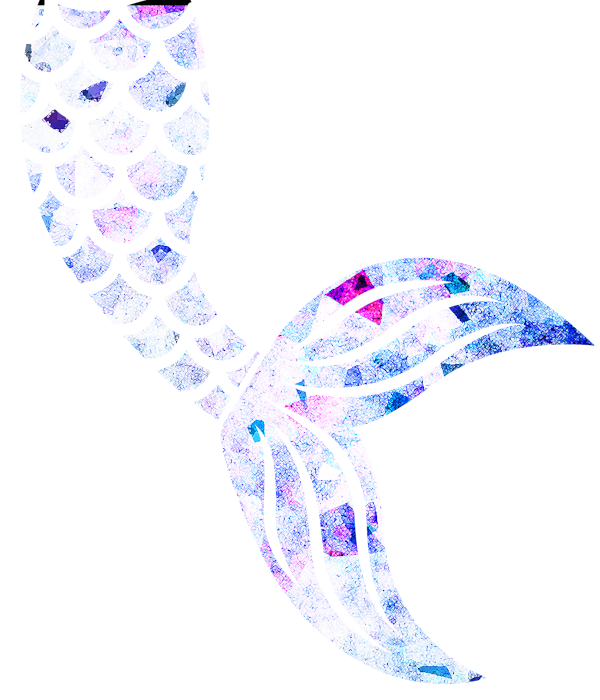
、と何度か呼ばれた声は懐かしかった。学生時代にも何度かあったと思いながら目を開ければ、頬に殴られた痕をつけたジェイドがこちらを覗き込んでいた。起き上がろうと体に力を入れれば、腕が後ろ手に縛られているのを悟る。ジェイドのほうは腕も足も縛られているようだったが、飄々とした顔をしていた。すこしだけ潮の匂いがする。港の近くか、それとも船か。またジェイドのいい『餌』にされたのだと悟って、一番に自分を哀れんだ。あの男に罪悪感なんて抱くのではなかった。
「よかった、意識は戻りましたね」
「ここはどこですか? そして今回は何をしているんですか」
「ここは輝石の国の南部地方の港ですね。倉庫の事務室に押し込められているところです。
今回は先日の彼が『副業』として関わっているグループに不正売買の疑いがあったんですが、なかなか尻尾が掴めず。放っておくには『我々』への被害が大きそうでしたので、からめ手を使ったみた次第です」
「はじめにホテルで再会したのも、偶然じゃなかったってことですか」
「仰る通りです。……まアしかしあなた、年々男の趣味が悪くなってませんか?」
「最初からです、放っておいてください」
ツンと顔を逸らせば、ジェイドは「おやおや」といつもの調子で笑ってみせた。ジェイドの言う不正売買が何なのかは知りたくもないが、おそらくここへ呼び出されてやって来るという体で潜入するのが、今回の彼の目的であったのだろう。つくづくいいように人を使ってくれると思いながら、痛む鳩尾に眉をひそめた。きっと痣になっているだろうから、あとでアズールに治してもらう羽目になる。
「あなたが目を覚ましましたので、僕はこの場を抜け出して少しばかり周りを探ってきます。一人で待っていられますね?」
「小さい子どもじゃないんですから」
「ふふ、いい子です」
ジェイドは囁くように笑って、荒縄の絡む腕を振る。足を拘束していた縄も蛇のように滑らかに動き、まるで「魔法みたいに」外れていく。ジェイドは「お守りです」などと言ってわたしの髪に唇を寄せた。きらきらと粒子が瞬いて周囲を浮かんでいるので、防衛魔法をかけてくれたのだろうが、それならこの腕の縄を解いてほしい。そういったのに、ジェイドは「そのまま大人しくしていてくださいね」と言って事務所から出て行ってしまった。防衛魔法をかけたときに痛みも緩和してくれたのだろう。鳩尾の痛みに眉を顰めることはなくなったが、こんな場所に置いて行かれて快適なわけがない。周囲に縄を外せるように道具がないかを思って探してみれば、お誂え向きなガラスの破片が目に入った。うまく使って自分の縄を外したときに、外から足音が聞こえた。
「くそ、やっぱりいないぞ!」
「探せ! まだ近くにはいるだろうからな」
慌てて身を隠して、正解だった。男たちはいなくなったわたしとジェイドを探しに、足早に部屋の扉を開けたまま出ていく。足音が聞こえなくなったのを十分確かめてから、わたしも事務所の部屋を出た。ジェイドがどこへ行ったのかはわからないが、なるべく人気の少ないほうへ行くべきだろう。周囲を警戒しながら付近を捜索していると、すこし向こうで人の声が聞こえてきた。どうもわたしの鳩尾に拳を叩きこんでくれたあの男のようだ。何かもめているのか、電話の向こうの相手としきりに言い合っている。ややあって切れた電話に悪態をつくと、頭を抱えながらその場にしゃがみ込んだ。わたしを攫ってジェイドをおびき寄せたことが『副業』の上司にばれ、叱責でもされたのだろう。
男はイライラとした様子で頭を掻きむしってから、近くにいた部下らしき別の男に早くわたしとジェイドを見つけるように指示を飛ばす。わたしは見つからないように来た道を後退した。すこし戻ったところで背後に人気を感じる。慌てて振り向けば、ジェイドだった。
「やっぱり出てきてしまったんですね」
「あんなところへ置いていくほうが悪いでしょう」
そう言えば、ジェイドはあいまいに笑う。わたしがあのままあそこにいて、ジェイドだけを捜索されるほうが彼にとっては楽だったのだろう。また数度殴られるかもしれないが、わたしを連れて歩く手間もなければ、探す手間も省ける。
「ここでの用事は終わりましたので、帰りましょう」
「さっさと連れて帰ってもらえますか。あの男、カンカンでしたよ」
「そうでしょうとも」
ジェイドはにっこりと人好きのする笑みで笑い、わたしを誘って工場の中を歩き始めた。マジカルペンでシグザウエルに似た銃を取り出し上段に構えると、足高に靴音を立てて倉庫の中を抜けていく。足音を聞きつけて襲ってくる男たちを一発ずつ確実に弾丸で昏倒させていくが、血が吹き出ることもないので、魔法痕から足がつかないように改造した魔導銃なのだろう。いくらか進んだところで、ジェイドが何かに気づいたように顔をあげた。
「あ、まずいですね」
「なんですか」
「あれの『上司』がここに見切りをつけたようです。あと数秒でここは吹き飛びますよ」
「は?」
「走って」
そう言うなり、ジェイドはわたしの腕をとって足早に走り出す。ジェイドとわたしでは足の長さが違うのでほぼ引きずられるような状態だ。なんとか倉庫の外へ出ると、ひゅるる、と間抜けに空気を切る音がした。ジェイドがわたしを抱えて物陰へ飛び込む。瞬間、どっと何かが破裂する音と追って腹の底を震わすような轟音が響いた。ぎゅうっとジェイドがわたしの頭を抱えるので、今は彼のコロンの香りしかしない。爆風が止むのを見計らって顔をあげれば、ジェイドの頬には破片が飛んできたのか、切り傷ができていた。
「ロケランでもぶっ放したんでしょうね、中のガソリンに引火させたのか。全焼させても、情報はこちらにあるので意味ありませんけれど」
ごうごうと燃え始めた倉庫からは蜘蛛の子を散らすようにわらわらと人間が出てくる。その中には蒼白な顔をしたわたしを攫った男もいた。煤に塗れて、見る影もない。
「少し離れたところで転移魔法をします。殴られた腹は、気分など悪くないですか?」
「今のところは。アズール先輩のところへは連れていってほしいですが」
「かしこまりました」
ジェイドはわたしを抱えようとしたが、断って歩く。遠くからサイレンの音が聞こえてくる。赤い炎に照らされたジェイドの顔はぬらりとして、あまり感情は読み取れなかった。倉庫を走り抜けたときからつないでいた手をジェイドは離してくれず、わたしも離してほしいと言えなかった。グローブごしのジェイドの手のひらは硬く、骨の感触のほうが強い。今度はわたしの歩幅に合わせて歩くジェイドは、社会人になって久しい大人の男には見えなかった。あのときに、戻ったようだ。
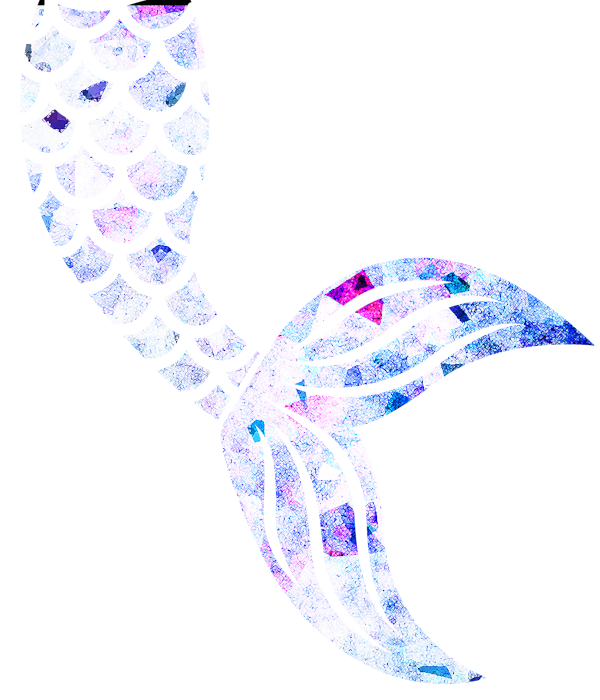
「、待って、すみませんでした、そんなに怒るなんて」
ジェイドを置いて先を歩いていたわたしの腕を、ジェイドは数歩で追いついて掴んできた。振り払おうとしても、ジェイドが離す気配はない。帽子の影に隠れたジェイドの顔は、珍しく焦って見えた。
「わたしは、他人に振り回されるのが嫌なんです。感情をあなたのいいように操られるのはきらい。そうやって心配させて、楽しいんでしょう?
もう、そういうの、見たくないんです」
「それは、すみませんでした。謝ります」
「いりません。学園長へ言って、モストロも辞めます。
そして好きなだけ、危ないことをしたらいいじゃないですか」
わたしはもう関係ないわ、そう言って踵を返す。それでもジェイドは腕を離してくれなかった。いい加減にしてくれと、もう一度振り返る。しかし見れば、毒気を抜かれてしまった。そこにいたのはそれまでの飄々と、にやにやと、悠然と構えてこちらを見下ろしている嫌味な男ではなく、どうしたらいいかわからないとでもいうように、はくはくと唇を震わせるだけの一つ年上の、十七歳の男の子だった。わたしが驚いて息を吸い込んだ間に、ジェイドはぐっと握った腕に力を入れる。
「行かないでください。僕が悪かった、謝ります。
あなたをこうして助けて見せれば、いいところが見せれるかと思い、あなたに怖い思いを……」
「……別に怖いことが嫌なわけじゃありません。ただ、わたしの感情を振り回されるのが嫌なだけです」
「どうしたら、許してくれますか?」
ジェイドの問いかけは必死さを孕んでいて、彼のそんな表情は見たことがなかった。思えば、あれも彼の手の内だったのかもしれない。今となってはもうわからない。ジェイドは絶対に真実を話さないだろう。ただ、わたしはそんな必死さを見せたジェイドを、好ましいと思ってしまった。そうやって彼の尾の内に、絡めとられたのだ。
「……どうして、こんなことをしたのか。その理由を教えてくれれば」
そう聞けば、ジェイドははにかんだ。彼が長身を曲げてぐいっとわたしの耳に唇を寄せる。わたしの問いに、自身が許されたのだと理解したからだろう。頬を滑った指先は、少しだけ震えていた。
「あなたが欲しいから、見てほしかったから」
鼻先が振れるほどの距離で見たジェイドの瞳は、滲んでよく見えなかった。そのまま、彼に呼吸を奪われてしまったから。わたしが問いかけをした理由も、ジェイドを拒まなかった理由も、馬鹿らしいほどに明白だった。
ジェイド・リーチが好きだった。
4
アズールは相変わらずのうさん臭さで、わたしの怪我も治してくれたし服も新しいものを買ってくれたし謝罪もしてくれたけれど、やっぱりそれでもうさん臭かった。ジェイドに嵌められた男は到着した警察にあのまま捕まったそうで、かつアズールたちは欲しかった情報をまんまと手に入れることができた。彼らはまた楽しく暗躍するらしい。わたしは素直な質なので、アズールという知り合いがいなければあんな社会の暗部があることなど、絶対に知らずに生きていただろうと思う。関わりたくない。
取引先の男が違法魔法薬の密売をしていたという社内のニュースを聞き流し、最近付きまとわれていたという情報を手に入れた刑事たちに曖昧な返答をし、普通どおりの日常を送る。今のわたしの日常には、ジェイドはいないのだ。ただ久しぶりに握った彼の手は変わらず大きくて、すこし感傷的になってしまっている。
エースかデュースを誘って飲みに行こうかと思ったけれど、あんな派手な事件があった後では二人とも忙しいだろう。もしかしたらぬるぬる会話を逸らすタコとやりあっているかもしれない。金曜の夜だったのでわたしは一人で飲みに行って、ぶらぶらと帰ることにした。しまったなと思ったのは、先日あの爆発から逃げた際に履いていた靴を今日も履いてきてしまったことだ。ヒールの高さのわりに歩きやすかった靴は、そのヒールがぽっきりと折れてしまって、わたしは途方に暮れていた。
通り道の公園でベンチに座り、折れたヒールを眺めてぼんやりとする。アズールに言ったら、この靴も弁償してくれたりしないだろうか。多分、あの日にあんな風に走ったりしたから折れたのだ。
街頭のすくない公園からは、月がこうこうと光って見える。夜風に当たって酔いはほぼ冷めたが、感傷的な気分は直らないままだった。帰り道の見つからないままNRCを卒業して、五年以上経つ。学園長はのらくらしながらも帰り道を探してくれており、後見人として彼の養子にしてもらったりもした。エースやデュースのような友人や、先輩たちにも恵まれているし、仕事だって住む家だってある。けれどしかし、わたしは元の世界へ戻りたいのだ。
ジェイドが生家の稼業を継ぐと言った。そして彼はわたしに一生そばにいてほしいと言った。それはわたしが元の世界に戻りたい気持ちと相反するわけでもなく、ただわたしは、元の世界かジェイドか、選ばなければいけない立場だった。それだけのことだ。今よりもう少し子どもだったから、ジェイドがわたしを理解せず譲ってくれないことが腹立たしかったし、ジェイドも同じだったろう。
ジェイドと、手をつないで歩くのが好きだった。山へ一緒に出掛けると、足もとの悪い岩場などではよく手を貸してくれたし、モストロ・ラウンジの背の高いスツールから降りるときにも手を差し出して支えてくれた。モストロの片づけが遅くなり帰り道をオンボロ寮まで送ってくれるときも、ジェイドはわたしと手をつないでくれた。ジェイドの手のひらはとても大きくて、いつもわたしの手のひらをすっぽりと包み込んだ。肌ざわりのいい絹のグローブごしの手も、ひんやりした体温の感じられる手のひらも、どちらも等しく好きだった。
ジェイドは山が好きで、一緒に登るときにはわたしもでも行けるような難易度の山を探してくる。わたしと行くための山は一人では登らず、取っておいてくれるところが好きだった。フロイドとアズールのことが大好きで、二人のことを話すときの語り口が好きだった。きのこだとか、海の中になかったものに興味津々で、好奇心を抑える気もないところが好きだった。夢中になればそのことしか目に入らなくなって、わたしを放っておくところも仕方がないと思っていた。喧嘩したときに謝りもせず、ぶずっとした顔で隣に座ってくるのでいつも仕方がないなって、本当に駄目な男だなって思っていた。
ジェイドとするキスが好きだったし、ベッドの中でまどろむ時間は幸福だったし、それが当たり前になることは居心地がよかった。だから彼がわたしの気持ちを理解してくれないこと、受け入れてくれないことがどうしても許せなくて、憎くて、そして彼の気持ちを受け入れることのできない自分が、嫌いだった。
こつこつと足音がして、すこし向こうに長身の人影が見える。ジェイドも仕事帰りのようで、すこしくたびれたスーツを着ていた。彼はわたしのところまで来ると、わたしの膝を覗き込んだ。血がにじんでいたからだ。
「転んだんですか?」
「そうですね、この間履いていた靴のヒールが折れたので」
「おやおや」
ジェイドは小さく笑うと、こちらに背中を向けた。負ぶってくれるということだろう。そのままその首の腕を回すと、ジェイドは軽々と立ち上がって、わたしの折れたヒールの靴を右手に持つ。私の太ももを支えるジェイドの手は相変わらず大きくて、背中からは彼のコロンとすこしの汗と土埃の匂いがした。
「まだお見合い続けているんですか?」
「そうですね、ぼちぼち」
「いい人いました?」
「あんまり」
ジェイドは苦く笑いながら月明りの道を歩く。わたしは、ジェイドが道端で他人にひどいことを言われていたら、そんなことはないって慰めたい。ジェイドはわたしが怪我をして歩けなくなったら、負ぶって帰ってやりたい。男と女の関係でなくてもわたしはジェイドが大切で、だからわたしたちはお互いに、きっとなんでもいい。ただ、優しくし合う口実が欲しいだけなのだ。でもそれは、ジェイドとわたしにはどうにも手に入れづらく、それが悲しい。
「わたしのいた世界の俗信に、死んだら川を渡るっていうのがあるんですが」
「へえ、レテの河のような?」
「ええ。それで、女はその川を、初めて抱かれた男に背負われて渡るんですよ」
「……ふ、それは、また、重いですね」
「ふふ」
少し引いたようなジェイドの声に、わたしは笑って彼の襟元に額を寄せる。いやに広い公園の道は月明りに照らされて、まるで水面のように淡く地面が光っていた。わたしが譲るのか彼が譲るのか一生そのままか、それとも別の答えが見つかるのか。わたしは、今でもわたしを探しに来るジェイドに甘えながら、いつも思っている。
「まあでも、それなら。あなたの場合は僕が背負うことになりますね」
初めての男がずっと忘れられないって、本当に最悪だ。この先どうなろうと、わたしはこの男を一生引きずりつづけるのだろう。この男を愛した事実も愛された事実も、なくすことはできないのだろう。
「ジェイドのばーか、嫌いです、わたしのこと今でも好きなくせに」
「それはこちらの台詞です。いい加減に帰ることが諦められませんか」
「諦めるわけないでしょう。ジェイドこそ、マジョリティな結婚して実家の仕事継ぐって、諦めましたか?」
「ハハ、無理です」
ジェイドのすげない返事に笑って背を逸らす。危ないなんて言いながら、ジェイドは公園の道をことさらゆっくりと歩いて行った。いつか帰り道が見つかりジェイドは結婚し、わたしたちはお互いに優しくすることが許されなくなる。
「迎えに来なければ、殺しますので」
「それは熱烈だ。期待してしまいます」
優しくするのに、理由がほしい。わたしはただ、あなたとこの世界を生きてみたかったんだ。

掴みやすい足首
ディヴィ・ジョーンズと人魚が共謀して、
そして、彼女を海の底に引きずり込むのか?
先日大手企業の営業部の男が違法魔法薬の取り扱いで逮捕されたのだが、どうにもその逮捕までにこのタコが一枚嚙んでいるようで、その情報を聞き出して来いと記者室から蹴り出されてきた次第である。同じカレッジの好だろうなんて上司や同輩は好き勝手なことを言うが、NRCの卒業生で同校の徒でよかったと思う人物など片手で数えるほどしかいない。もちろん、目の前のタコはそこから除外されている。
蹴り出されたエースがアズールのところへやって来るのは珍しいことではないので、目の前の銀髪の麗人はエースの相手を適当にしながら、無難な類の仕事を進めている。エースは出された茶を飲みながら、座り心地の良すぎるソファに身をうずめていた。
「そういえば、お宅のリーチさん、物騒のほうですけれど。まだ監督生に未練があるんですか?」
「物騒とは懐かしい名を……。そもそもですが、人魚とは一途なものですよ。それは、思いが残っていても不思議ではないかと」
「でも、を振ったのはジェイドさんのほうでしょ?」
エースが聞けばアズールはPCの画面から目線をあげて、ふ、と笑った。まるで仕方のない、察しの良くない、出来の悪い子どもを見るような目だった。
「これは僕の推測ですが、『仕方がなく』振ったのだと思いますよ。ジェイドとこういう話をしたことはありませんが、愛しいつがいが『自由になりたい』と泣いたなら、叶えてあげたくなるのが男の性です」
「マアそう言われればそうですけれど。その割に未だにちょっかい出して、矛盾でしょ」
「おやおや」
アズールは慈愛のこもった顔で笑う。エースはアズールのこういう顔が甚く苦手であった。こういう顔をされると、同年代の男には全く見えず、得体の知れない生き物に思えるのだ。自分とは生きている世界も見えているものも、違っているような。
「叶えてあげたいと思うことと、叶えるかどうか。これは別の話ですよ」
「……サイアク。に気を付けるように言っておきます」
「マ、手遅れでしょうね」
「は?」
アズールはキーボードから手を放し、ぎっと音を立てて椅子の背もたれに背を預ける。その姿はまるで海の魔女然としており、背後の窓から振り注ぐ光には赤さの欠片もない。これでは、海の中にいるようだ。思わず喘いだ自分を自覚して、エースは背筋を凍らせた。
「ジェイドは掴んだ獲物を離すような男ではありませんからね。彼女が未だに元の世界とやらに帰れないのは、人魚の執念でも巻き付いているのか、縁を上書きされたのか……。クロウリーは優秀な魔法士ですが、苦労していると思いますよ。人魚の情念は深いので。
マア、彼女のほうもまんざらでもない様子ですし、僕は静観して久しいのですが、エースさんは興味がおありで?」
「いやぁ、ないですね……。関わりたくねー……」
これこそ藪蛇と言っていい情報に、エースが顔を引きつらせると対照的にアズールは薄ら寒く、にっこりと笑った。
ただ、とエースは思う。きっとこの人たちは思ってもみないけれど、うちの監督生は、いつも思ってもみない突拍子もないことをやってのける。だから。
「マ! ジェイドさんの思う通りになればいいですよね! オレ応援してます!」
こんな心にもないことが言えるのだ。人魚に足首を掴まれた人間が藻掻かないなんて、そんな保障はどこにもない。エースの知っている監督生は、ディヴィ・ジョーンズからも逃げ出すような、そんな破天荒な女だ。
inspire by Genesis "Dodo / Lurker"