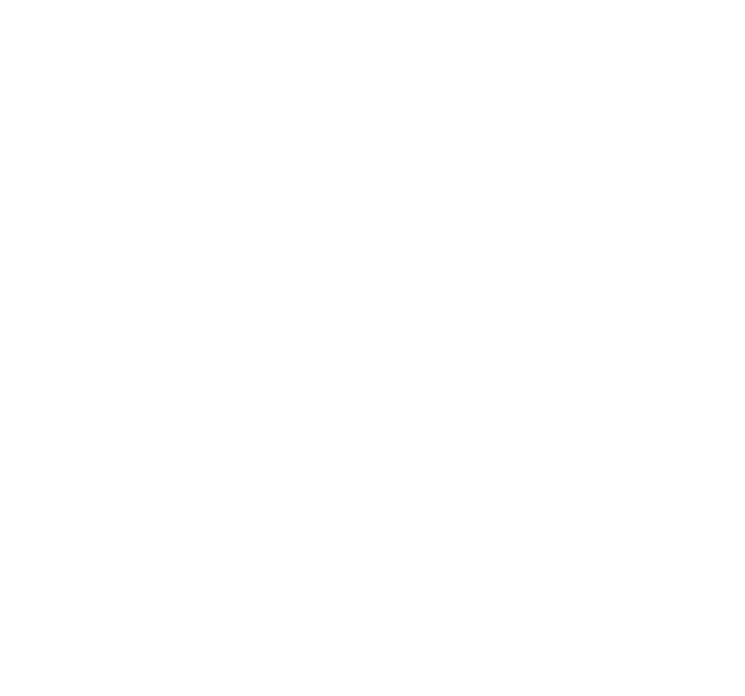夏油傑くんは、小学一年生の子どもとは思えぬほど大人びていて、昼休みには教室の片隅で読書をしたり窓の外を眺めたりするような、物静かな子だった。
他の生徒とはケンカはもちろん馴れ合うこともないので、一学期の始めの頃は、そんな夏油くんのことを気に掛けていた。クラスに馴染めないのではないか、と。しかし本人に学校生活について尋ねても、
「楽しいですよ。心配してもらうようなことはありませんので大丈夫です」
と、流暢な敬語で返されるだけだった。
周りの子たちに夏油くんのことを聞いてみれば、みな一様に「良いやつ」「いろいろ知ってて面白い」などと肯定的な印象を語るので、教師が見ていないところでは彼も他の子たちと年相応の交流をしているのだと胸を撫で下ろしたのを覚えている。
――子どもだけど、子どもではない。彼の体の中には六歳の少年ではない何かが巣喰っているのかもしれない。
そんなふうに感じ始めたのは、家庭訪問の時に夏油くんの母親が告げた言葉がきっかけだった。
「あの子、たまに妙なことを言いませんか?」
妙なこととは、と尋ねれば、母親は視線を下げ、ティーカップを両手で握り締めた。
「こんなこと先生に言うのもおかしいのですが……でも、他に誰に相談すべきかも分からなくて――」
ためらっている様子だったので、私でよければ何でも聞きますよと言葉を促すと、母親は再び視線をこちらへ戻し、声をひそめた。
「あの子にしか見えないものが、見えているみたいなんです」
その言葉を咀嚼するのに、少し時間を要した。
「それはつまり、幽霊が見えるということでしょうか?」
「……ええ、おそらくは」
ああ、なるほど――と思った。
霊感が強い人というのはたまにいる。私の叔母もそうだった。中学の頃、修学旅行で撮った写真を何気なく見せたことがある。それまでニコニコと微笑んでいた叔母が、一枚の写真を見た途端に真顔になった。どうしたの、と尋ねれば、叔母はこの写真を預かってもいいかと言った。いいよと答えれば、叔母は写真を懐に仕舞って、何事もなかったかのように私の修学旅行での思い出話について聞き始めるのだった。その数年後に、あの時のあれは何だったのかと聞けば、「霊がね。たくさん写ってたのよ。水に飢えた人たちだったからね、家で毎日お水をお供えしてたら、表情もだんだん和らいでいって」と、どこか愉快そうに語った。叔母に霊感があるのだとは聞いていたけれど、自分の撮った写真にそういうものが写っていたことがショックで、そして、事もなげに語る叔母の姿が少し奇怪に思えて、私はその後しばらく写真を撮るのが怖くなった。
夏油くんが叔母と同様に、見えざるものが見える側の人間だと知って、私は別段驚かなかった。むしろ納得した。彼がみんなとは別の方向をじいっと見つめている様子を、今まで何度も見てきたからだ。
けれど夏油家から帰宅して、夏油くんの母親の怯えた様子や、夏油くん自身のこれまでの学校での姿を思い起こすうちに、どこか薄気味悪く思えてきた。何かが起きそうな、そんな予感すらした。
その頃の私は、平穏とは言いがたい生活を送っていた。産休に入る同僚の引継ぎ、これは言うほど大変なことでもなかったかもしれない。それよりもややこしいのは、実家の母と祖母の間に起きた介護問題の仲裁、別れた元彼のストーカー疑惑などだった。一筋縄ではいかないことばかりで、すべての物事から解放されるにはどうしたらいいのかと、本気で考えていた。
「先生」
仕事を終えて帰宅しようと職員室を出ると、暗い廊下から小さな影がふらりと現れた。驚いて息を呑むと、職員室から漏れた明かりに照らされて、暗闇から夏油くんの顔が浮き上がってきた。
「どうしたの夏油くん、こんな時間まで学校に……親御さんが心配するよ。早く家に――」
「先生」
「先生が家まで送るから、ほらこっちにおいで」
手を伸ばして夏油くんの腕を掴めば、彼は「先生」と囁くような声で言った。
「今日は家に帰らない方がいいですよ」
彼の言葉が理解できなくて、普段は生徒の前で出さないような低いトーンで「え?」と漏らしてしまう。
「家に帰らない方がいい理由。思い当たること、あるんじゃないですか?」
この子は何を言っているんだろう。その時の私は、夏油くんの言葉の意味を深く考えることよりも、担任として一刻も早く生徒を家に送り届けなければという義務感にとらわれていた。そうして、半ば引きずるように夏油くんの腕を引いて車に乗せると、慌ただしく学校を出た。
夏油くんを自宅まで送り届けると、彼の母親は何度も頭を下げた。すみません、ありがとうございました、と言う割には、息子を探して駆け回ったような様子は見られなかった。もしかすると、こうやって夏油くんが遅くに帰るのは珍しいことでもないのかもしれない。そんなふうに思いながら車に乗り込み、発車させようとサイドミラーを確認すると、こちらをじいっと見つめる夏油くんの姿が映っていた。
『今日は家に帰らない方がいいですよ』
あの言葉が耳に蘇った。夏油くんは変わらず、感情の読めない目でこちらを見つめている。途端、背中に冷たい何かが這うような感覚に襲われた。
――何なの?
言いようのない不気味さや釈然としないことへの苛立ちを抱えながら、私はアクセルブレーキを踏んで車を出した。
そしてその日。私は、一度死んだ。
帰宅して、部屋に入ったところまでは覚えている。物音がして振り返ると、元彼が立っていた。片手に刃物を持っていた気がする。いや、そうだ。刺されたんだ。いわゆる滅多刺しというやつ。私、そんなに恨まれるような別れ方した覚えはないんだけどな。そんなことを思いながら意識を手放した気が、する――。

物心ついた頃から、周りにいる同い年の子たちが幼稚に見えて仕方なかった。小学校に入学してからはもう地獄で、群れなきゃ行動できない女子、くだらないギャグを言わなきゃ立ち位置を確立できないと思っている男子、学校という狭い空間しか知らないくせに世の中を悟ったように講釈を垂れる新任教員たちに囲まれて、私は自分の世界が腐っていくように感じていた。
その中で漠然と、「もしかするとあの子も同じだったのかな」と思った。“あの子”とは誰なのか、自分でもはっきりと分からない。それでも私の中には、物心つく頃からずっと“あの子”がいた――。
「思ったより早かったなあ」
十歳になり、冷めた目で世の中を見ることにも少し飽きてきて、周りの大人が望むような子どもらしさを身に付けるのも賢い生き方なのかもしれないと思い始めた頃だった。
公園のブランコで一人体を揺られていると、どこからともなく現れた男子高校生が、私を覗き込んでそう言ったのだ。
「……あ――」
私は彼の姿に、“あの子”だ、と思った。
「その様子だと、おぼろげながらもあるんでしょう。前世の記憶が――ねえ、先生?」
夏油傑くん。かつての私――彼の言葉を借りるなら“前世の私”の教え子だった、見えないものが見える男の子。私に死の前兆を告げた、男の子。
「今の先生は十歳ぐらいかな? ということは、あの事件のあとすぐに生まれ変わったんですね」
高校生になった夏油くんは、あの頃より背も髪も伸びていて。でもその妙に大人びた口調や表情筋の使い方は相変わらずで。そんな彼が言った「生まれ変わり」という言葉に、私は幼少期から抱えていた違和感の正体が分かった気がして、妙に納得してしまった。同時に、前世での記憶が堰を切ったように蘇ってきて、ブランコの鎖をしっかり握っていないと地面に倒れそうになるほどに視界がぐらついた。
「大丈夫ですか」
夏油くんは肩に下げていた通学バッグを地面に置き、ゼェゼェと荒い呼吸を繰り返す私の隣にしゃがみ込むと、落ち着かせるように背中を叩いてくれた。彼の通学バッグに付けられた校章は、どこの学校のものなんだろう。近隣の高校のものではないし、今までに見たこともない。
「……どうして?」
ぽつりとこぼした私の言葉に、夏油くんは首を傾げた。
「どうしてはっきり伝えてくれなかったの? あの時……私が殺されるって。死んでしまうから、家には帰らない方がいい、って。夏油くんには結末が分かってたんだよね?」
十年前、夏油くんは前世の私に言った。今日は家に帰らない方がいいですよ、と。彼の自宅まで送った私を、物言わぬ目でじいっと見つめていた。
夏油くんは、視線を逸らしてふっと笑う。
「確信があったわけではないですから。いわゆる、嫌な予感がする程度で」
「そういうふうには見えなかったけど……」
予感程度なら、あんな言い方しない。あんな視線を向けない。
黙り込んだ夏油くんは、ゆっくりと立ち上がると、私の隣のブランコに腰掛けた。キィ、キィ、と鎖が軋む音が公園内に響く。そうして夏油くんは、ふう、と吐息をひとつこぼしたのちに言った。
「確かめたかった。あの時、先生の背後に黒い影がまとわりついていて、ソレがしきりに言っていたんですよ。こいつを殺すよ、殺すよって。それで、その日は『今日殺すよ』と言っていたので。あの頃は自分にだけ見える異形の正体がよく分かっていなくて。そんな得体の知れないモノが言うことなんて信じられないという思いと、もしかすると本当に起こり得ることなのかもしれないという思いが入り混じって。……先生で、実験しようとしていたのかもしれません。結局、あの黒い影の言う通りのことが起きて、先生は死んでしまった。今思えば、あの影は犯人――先生の元恋人の生き霊だったんですよね」
できればもう思い出したくない光景だった。自分の最期。けれど夏油くんの言葉によってそれらは掘り起こされ、私の呼吸は再び浅くなる。あの人はその後ちゃんと逮捕されただろうか。あんなに執念深い男だと分かっていれば付き合わなかった。親も、まさか自分の娘が殺人事件の被害者になるだなんて思ってもいなかっただろう。泣かせてしまっただろうな。今、どうしてるんだろう。
ふと顔を上げれば、夏油くんは様子をうかがうようにこちらを覗き込んでいた。
「それで……私で実験した結果は?」
私の声色から、これ以上自分を責める気はないのだと察したのか、夏油くんはどこか安堵したように表情を和らげた。
「確信しました。自分が、普通の人なら持ち得ないものを持って生まれてきたんだと」
あの子にしか見えないものが見えている。そう言った夏油くんの母親の、どこか怯えたあの声が、顔が蘇る。あのお母さんは、“持ち得ないものを持っている”と自覚した息子のことを受け入れたのだろうか。
「大丈夫?」
今度は私が夏油くんを覗き込む番だった。いろんな意味を込めた問いに、夏油くんはやんわりと笑んだ。
「ええ、はい。一般社会にいれば私は異質な存在ですが、今は少し変わった環境に身を置いているので、あの頃と比べれば生きやすいですよ」
「楽しい?」
「……え?」
不意な質問に、夏油くんは面食らったように目を丸めた。私も私で、そんな問いかけが唐突に口を突いたことに自分で驚きながらも言葉を続ける。
「あの頃の夏油くんって、この世を冷めた目で見てる感じだったというか、何か悟ったような子どもだったなあって」
「先生、私のこと気味が悪そうでしたもんね」
「だって子どもらしくなかったんだもん。……ごめんね?」
「別に気にしてないですよ。そういう目で見られることには慣れてたんで」
返答に困るような言葉をさらりと吐く夏油くんに、私は瞬きを何度か打つことで場を誤魔化した。
「子どもらしくないと言えば、まあ……今の私も同じなんだろうけど。あ、もしかして夏油くんも、前世の記憶を持って生まれ変わった人だったりする?」
「いや、私は違いますよ。ただ単にマセた気味の悪い子どもだっただけで」
ほら、またそんなこと言って。
ここは笑うべきなのかと戸惑う私を尻目に、夏油くんは喉奥をくつくつと鳴らして笑った。
「ねえ夏油くん。今、楽しい?」
笑う夏油くんの横顔に、私は再び聞いた。夏油くんは「あの頃と比べると生きやすくなった」と言っていた。生きやすいのと楽しいのとは違う。小学生の頃の夏油くんは、少なくとも私の目から見て、とても楽しそうとは言い難かった。だから高校生になった今の夏油くんはどうなのだろうかと、たった半年程度しか担任ではなかったくせに、教師心が疼いてそんなことを尋ねてしまった。
「すーぐるー!」
不意に飛び込んできた声に、夏油くんと私は目を丸めてその方へと顔を向ける。公園の入り口から手をぶんぶんと振る白髪の男子高生。夏油くんと同じ通学バッグを肩に掛けている。その隣には栗色のボブヘアの女子高生が、少し気だるそうにこちらを見ていた。
「おっまえ女児捕まえてなーにやってんだよー!」
「あーごめんごめん! すぐ行くよ!」
今にもこちらに向かって駆け出してきそうな白髪男子を牽制するように、夏油くんは手のひらを前に突き出しながらそう言った。けれどその顔には、小学生の頃の彼からは想像もできないような表情が広がっていた。
「友達、できたんだね」
夏油くんのそんな笑顔、見たことないよ。という言葉は呑み込みつつそう言えば、彼はブランコから立ち上がって言った。
「世界が変わったように思えるんです」
そうして、地面に置いていた通学バッグを持ち上げて肩に掛けると、こちらを振り向く。
「少なくともあの頃よりかは、笑えるようになりましたよ」
その言葉に、胸の内側がゆるんだ。ふっ、と笑えば、「その笑い方は全然子どもらしくないな」と夏油くんに指摘されたので、ニシシ、と歯を出して子どもっぽく笑ってみせた。すると夏油くんは突然何かを思い出したかのように「あ、そうだ」と目を見開く。
「先生にも見えてますよね。もっと言えば、持ってる側の人間だ。私たちと同じ」
言いながら、夏油くんは胸元のボタンを引きちぎった。
「今日のことを忘れないように、これ渡しておきますね。あと五年も経てば、きっと先生のところにもスカウトが来るはずですから。多分その時に、この校章を見せられると思いますよ」
渦が巻いたような紋様が刻まれたボタン。それを私の手のひらに置くと、夏油くんは眉尻を垂らして笑った。
「なんで、見えるって……」
夏油くんの言う通りだった。今世の私には、生まれながらにして霊感のようなものがある。でもそれは、前世での叔母が持っていた力とはまた少し異なるような気がした。単なる霊感ではない。霊は、私が見えていると気づいても、縋るように後を付いて来るぐらいで襲いかかってくることはない。けれどソレらは、見られていると気づけば歯を剥き出しにして飛びかかってくる。初めて襲われた時、「嫌だ!」と全身の力を込めて払いのけると、ソレらは灰のように消えていった。それからは対処方法を掴んだので、恐れる気持ちも次第に薄らいでいった。みんなが見えないものが見えている。これは、誰にも告げたことのない私の秘密だった。
「大丈夫。悪いことばかりじゃない」
夏油くんは腰を屈めて私と目線の高さを合わせる。そうして、宥めるような口調で言った。
「今は生きづらいことが多いかもしれませんが、呪術高専に行けば、少しは息がしやすくなると思いますよ」
夏油くんはきっと、私が自分の来た道を辿っていると思ったのだろう。その思い込みは間違いではない。私も、これがきっと夏油くんの歩いてきた道なのだと感じながら、今世を生きていたように思う。
あの時の私は、あっちにもこっちにも行けない中途半端さを抱えながら異形のモノと対峙する恐怖や孤独を知らなかった。だから、夏油くんの気持ちに寄り添う言葉はかけられなかった。異質な子どもだと思って、一線を引いていた。担任の先生だったのに。
でも今の夏油くんは、私の不安を少しでも拭おうと言葉をかけてくれている。罪滅ぼしなのかもしれない。前世での私の死を察しながらも救いきれなかったことに対しての。自らの力を確信するための実験台にしたことに対しての。
「それでは先生、あっちで待ってますね。また会えるのを楽しみにしています」
夏油くんが同級生と合流して雑踏の中へと溶けていくのを、私は呆然と見送った。
乗り手を失ったはずのブランコがギッ、ギッ、とぎこちなく揺れている。見れば、小さな子どものような姿をした異形のモノがブランコを漕いで遊んでいた。無害そうなソレから視線を逸らし、手のひらのボタンを見おろす。夏油くんの言うことが本当なら、いつか私も彼らと同じ制服と通学バッグを身につけて、“あっち”の世界で生きることになるのだろう。
想像してみた。数年後の自分の姿を。そしたら少し、胸が軽くなった。
「……あー、なんかそれって悪くないかも」
手にした制服のボタンをポケットに仕舞うと、ブランコの鎖を掴んだまま後ろに下がり、思い切り地面を蹴り上げる。ブランコはぐんぐんと高さを増していく。あははと笑いながら漕ぐ私を見て、小さな異形は口をぽかんと開けていた。
「世界が変わったように思う」と言って穏やかに笑んでいたあなたが、再び世界を変えようとするまで――あと十一年。

混沌渦巻く世でも新しい命は芽吹き続ける。
新宿での百鬼夜行で夏油くんがいなくなってから、私は死んだように生きた。その中でお腹に宿っていたモノに気づいた時、「先生」と呼ぶ夏油くんの声が聴こえたような気がする。そうだ。夏油くんは“こっち”の世界で再会してからも、ずっと私のことを先生と呼んでいた。美々子ちゃんや菜々子ちゃんは、なぜ夏油くんが私をそう呼ぶのか理解していなかった様子だけれど、夏油さまがそうするなら、と彼を真似て私を「先生」と呼んでいた。
お腹の子がこの世に生まれ落ちた時、彼女たちは「夏油さまの子どもだ」と涙した。私は我が子を初めて腕に抱いた時、ああ、廻ったんだな、と思った。そうして、あの時の彼が私に言ったのと同じ言葉を紡ぐ。
「思ったより早かったんだね」
――ねえ、夏油くん。今世でのあなたは、何を変えたい?