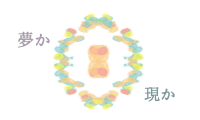 「だからちゃん、それは本来の実弥さんじゃないんだってば!」 「だって禰󠄀豆子を何度も刺したし、背中に"殺"って入れてんだよ? 目もバッキバキだし、やっぱイカれキャラ枠だとしか思えないわあ」 「イカ……だめそんなこと言っちゃ!」 スイミングスクールで出会ったタミちゃんとは、もう十年来の付き合いになる。進学先の高校は違うけれど、こうして市民プールにやって来てはぺちゃくちゃと喋りながら泳ぐのが、毎週末の楽しみだった。 タミちゃんは昔から漫画やアニメが大好きで、その趣味に付き合うことも多かった。タミちゃんの近ごろのお気に入りは、もっぱら鬼滅で、私もそんな彼女に半ば監禁される形でアニメを全話見たのち、劇場版も見てほしいと映画館へ連れて行かれた。 人からおすすめされるものを素直に受け入れることができない天邪鬼な私は、煉獄さんに涙するタミちゃんの隣で、「タミちゃんは夢中になれるものがあって良いよな」とどこか冷めた気持ちでスクリーンを眺めていた。 今も、プールサイドに座って、いわゆる推しの不死川実弥について熱く論じるタミちゃんに、少しいじわるな返しをしてしまった。 「……言えない。ネタバレしたくないから言えないけど、でも実弥さんは本当に優しいの。いいからちゃんは早く無限列車以降の本編読んで!」 はいはい、と気のない返事をしながら、私は体を伸ばした後、タミちゃんを残してプールに入る。 夢中になれるもの。いつか私も、誰かに共有したいほど胸を熱くさせるものと出会えるのだろうか。 「これだけは教えたげる! おはぎが好きなの!」 タミちゃんの声が響く。振り向くと、タミちゃんはプールサイドに立って、目を輝かせている。 「ちゃんも好きじゃん、おはぎ! 実弥さんと同じだよ!」 ねえ、タミちゃん。完全に恋する女の子の顔だよ。それに私が好きなのはおばあちゃんのおはぎ、引いてはおばあちゃんの作るものであって、無類のおはぎ好きというわけではない。 ちょっとその点だけは訂正を入れないと、と思い、タミちゃんのいる方へと水中を移動していたときだった。すぐ傍を、背泳ぎをしている男性が通る。その腕が私の後頭部にぶつかり、驚きと痛みでバランスを崩し、足を滑らせてしまった。いや、滑らせるというよりも、引っ張られる感覚に近い。 ――なに、これ……。 タミちゃんの声が遠ざかる。水泡が視界を遮り、ゆっくりと暗転していく。 足首を引っ張り上げられる感触で目が覚めた。見える景色が逆さまだからなのか、頭を打ってすぐだからなのか、何が何だか状況がすぐに飲み込めない。 「おやおや? 人間が釣れたようだねぇ」 そんな逆転した視界に入ってきたのは、外国人のような出立ちの男性。ベージュっぽい明るい髪に色素の薄い肌、虹色の瞳には何かの文字が刻まれている。 私は足首を掴み上げられ、両腕をだらしなく垂らして宙ぶらりんの状態だった。 「君、川で溺れていたんだよ。一体こんな森の中で何をしていたのかなぁ?」 「……森の中? え、なんで……私プールにいたのに」 「ぷーる? それって何?」 頭に血が昇って、視界が霞んできた。男性はそれに気づいたのか、私の背中に手を当て、ぐっと押し上げる。いわゆるお姫様抱っこの状態になり、思わず男性の顔を見上げてしまう。 これは漫画のような展開。タミちゃんに借りた往年の少女漫画にあった描写だ。 「なんだい、そんなにまじまじと見つめて」 男性はくすくすと笑いながら、傍にあった岩の上に私を横たえた。私は体を起こし、男性をじっと見つめる。 この人、頭から赤いペンキみたいなの被ってる。そして瞳の文字は―― 「上弦の……弍……?」 思わず口にしたこのフレーズ、似た台詞を聞いたことがある。そうだ、タミちゃんと観に行った鬼滅の映画だ。炭治郎が鬼と対峙した時に言ってた。上弦の参。こういう目だった。そうだ、猗窩座。三番目に強い鬼だって、タミちゃんが言ってた。ということは、この人は二番目に強い鬼―― 「の、コスプレの方ですか?」 「え? こすぷれ?」 男性は首を傾げ、片手に持っていた扇子で口元を隠しながら笑う。 「面白い子だねぇ」 「違うんですか? え、もしかして他にも……猗窩座のコスプレの人もいます?」 周りを見渡すも、木しかない。私たち以外に人の気配はない。どうも森の奥深くらしい。 「君は猗窩座殿を知っているのかい?」 「知っているも何も、さすがによく理解してない私でも彼には怒りが湧きました。あのまま陽に焼かれて死んじゃえば良かったのに」 「……」 「でもタミちゃんいわく、猗窩座にもつらい過去があるって――あ、すみません話しすぎましたね」 男性はもう笑っていなかった。扇子の向こうから、じっとりとした目で私を見据えている。 「君、名前は?」 「……あの」 「あ、先に名乗るべきだよね。俺は童磨」 「、です」 「ちゃんかあ。よろしくね」 童磨さんは先ほどの表情とは打って変わり、にっこりと微笑んだ。 「その格好だと寒いでしょ。俺の寺院へおいでよ。ここからすぐ近くなんだ」 言われて、私は自分の体を見下ろす。スクール水着に、頭は水泳キャップを被ったままだった。 ――やっぱり私、プールにいたんだ。なのに、どうしてこんな森の奥に? 「ちゃん?」 知らない人の家に行くなんて絶対だめだ。でも確かに、吹きつける風に体温が奪われていく。 とりあえず首筋を温めるためにも水泳キャップを外し、童磨さんを見上げる。 「スマホ、貸していただけませんか?」 「すまほ?」 「あ、じゃあすみません。電話でも」 「電話?」 「え?」 とぼけているのだろうか。童磨さんはスマホも電話も知らない、という顔をして首を右に左に傾けている。 「君はおかしなことばかり言うね。もしかして、違う世界からやって来たのかなあ」 違う世界からやって来たのかな。 その言葉が頭の中で何度も繰り返される。いやでも日本語通じてるし、この人がちょっと変わっているだけなのかも。けど、どうして私はこんなところに。これは、夢? 「おっと、何してるのちゃん」 私は自分の頬や腕を手当たり次第に摘んだ。いてっ、と声が漏れる。 「これは夢なんです! 目覚めないと……」 「夢?」 「すみませんが、童磨さんも手を貸してください!」 そうだ、炭治郎が夢から覚めるためにやったことがある。あれを試せば、私も目覚められるかもしれない。 「童磨さん、私の首を締めてください!」 「ええっ?」 「大丈夫。夢の世界の死が、現実の目覚めにつながるんです!」 「ちょっと待ってよ、俺は君を――」 「早く!」 童磨さんの手を掴み、自分の首に持って行こうとした時。頬にピリッとした痛みが走った。 「ごめんよ。引っ掻いちゃったね」 見ると、童磨さんの爪は鋭く尖っていた。その指先が私の頬に当たってしまったらしい。いえ、と言いつつ頬に手を当てて見ると、血が出ていた。 「やっぱり君、稀血なんだねえ」 顔を上げると、童磨さんは恍惚な表情を浮かべていた。 稀血って何だっけ。そう思っていると、童磨さんの手が私の頬に触れ、指先で血を掬った。 「君のことを喰うつもりはないよ。どうも心が綺麗な子のようだからね。側に置いて、死ぬまで面倒を見てあげる。ただ毎日、少しだけ血を飲ませてくれるかな?」 そうして指についた血を舐める童磨さんの姿に、気味の悪さを感じてしまう。 どうやら童磨さんはコスプレイヤーではなく、かなり危ない人らしい。 震え始めた私の体に、童磨さんは「大丈夫?」と言って、着ていた羽織を掛けてくれた。お香のような香りがした。 森林の隙間から光が差し込む。見上げると、先ほどまで薄暗かった空に、うっすらとした朱色が滲んでいた。童磨さんは扇子を広げ、光が当たらないようにしている様子だった。 「夜明けが近いな。さあちゃん、行こう」 差し伸べられた手を掴む勇気は全くなくて、私は膝を抱えたまま、首を横に振る。 「童磨さん、怖いです。血を飲ませろなんて怖すぎます。あなたは一体、何者ですか?」 童磨さんはまた、あの無の表情になった。空虚な目で私を見下ろしている。 「猗窩座殿のことも、鬼が陽光に弱いことも知っている。鬼殺隊でもないようだし……君こそ、何者なんだい?」 押し黙ったまま見上げていると、童磨さんはふっと表情を変える。そうして、茶目っ気たっぷりに笑った。 「なんかもう面倒だから、死なない程度に足先とか斬り落としちゃおっかな」 扇子が振り上げられる。よく分からないけれど、この扇子が当たったらきっと、頬を引っ掻かれた時の比ではないほどの痛みが襲うはず。 目を瞑った時、風向きが変わった気がした。浮遊感に瞼を開くと、傷だらけの胸元が飛び込んできた。見上げてみると、銀色の髪に鋭い目つきの男性がこちらを一瞥した。 「おい女、鬼と何してたァ」 言いながら、私の体を抱きかかえたままものすごいスピードで森の中を駆け抜けて行く。木々の隙間から差し込む日差しが眩しい。童磨さんの姿は、もう見えない。 森を抜けると、そこは朝の光にあふれていた。辺り一面に広がる田畑の合間に、ぽつりぽつりと民家が点在し、その向こうには小高い山がある。その山の上に、太陽がしっかりと顔を出していた。 男性は私を下ろし、足の先から頭のてっぺんまで無遠慮に見てくる。童磨さんの羽織を着てはいるものの、その下は水着だし、裸足だ。 「家は?」 私はうつむいたまま、力無く首を振る。 もうわけが分からなかった。夢にしては長すぎるし、鮮明すぎる。匂いだって分かる。今だって何か甘い、あんこみたいなにおいがするし。 ――あんこ? もしかしてこの人って……。 ふと顔を上げると、怪訝そうに見下ろしていた男性は少し驚いたように目を見開いた。 「不死川実弥」 「あァ?」 「の、コスプレの方ですか?」 「こすぷれ?」 ――ああ、童磨さんと同じ反応だ。コスプレイヤーじゃないの? 何なの? 夢なら覚めて。夢じゃないならこれは何なのか誰か教えて。ねえ誰か、ねえ、タミちゃん。 「まあいい。お前、どっかその辺の民家にでも身を寄せてろォ。俺はあの鬼を狩ってくる」 「行かないでください」 視界がぼやけ始めた。鼻の奥がツンとする。男性はギョッとした様子で私の顔を見る。 「なに泣いてやが――」 「あなたのことを知っています! 禰󠄀豆子ちゃんを刺した風柱、不死川実弥さんですよね」 「……あ?」 「背中に"殺"って入れてますよね」 ぐるりと背後に回ると、やっぱり背中に"殺"の文字が縫い付けられている。 「おはぎが好きらしいですね」 「あァ?」 不死川さんはこめかみに青筋を立て、私を睨みつけている。 ――ああこの目、アニメで見た目だ。怖すぎ。この人はコスプレイヤーじゃない、本物だ。あれ、二次元のキャラクターに本物も何もないのでは? いやもう面倒くさくなってきた。考えても仕方のないことは考えるなって、誰かが言ってた。煉獄さんだっけ。私も気付かないうちに、すっかり鬼滅脳になってしまってたみたいだな。 「何者なんだァてめえ」 ――タミちゃんが言ってた。不死川さんは本当は優しい人だって。 私は意を決したように不死川さんを見据える。 「夢なのか何なのか分からないんですけど、迷子になってしまいました。知っている人が不死川さん、あなたしかいません。お願いです、一人にしないでください」 「おいおい、何言ってんだ」 「じゃないと私、死んじゃいます。稀血らしいので」 そうだ、稀血は鬼に狙われやすい。童磨さんも物欲しそうに私を見ていた。 不死川さんは、これでもかというほど目を見開いた後、「わけ分かんねェけどよォ」と、ふっとその力を緩めた。 「そういうことは早く言え」 そうして私に背を向けると、その場で膝を突き、振り返る。どういう意味なのか分からず首を傾げていると、不死川さんは舌打ちをした。 「お前、裸足だろォが。背負ってやるから乗れェ」 その声色は存外穏やかで、少しも恐ろしくはなかった。吸い寄せられるようにその背中に体を預ける。あたたかい。"殺"と書いてある背中がこんなにあたたかいなんて、なんか、反則だ。 「やっと目覚めたか」 飛び起き、あたりを見渡す。立派な和室、清潔そうな布団、おいしそうな匂い。そして私の枕元で胡座をかいている、不死川さん。 「いやこれ……全然目覚めてないじゃないですか」 「誰がどう見ても目ん玉開いてるだろーがァ」 「目覚めても夢の中だ」 おかしいやつだな、と言いつつ、不死川さんはお盆を差し出す。そこにはご飯、味噌汁、焼き鮭に小鉢がきちんと並んでおり、湯気が立っていた。 「背負った途端に眠り込みやがったから、一旦うちに連れて来た。大したもんはねェが、とりあえず食え」 「これ、不死川さんが?」 「なんか文句あんのかァ?」 「ギャップ激しすぎません? 見た目的には絶対キッチンに立たないタイプじゃないですか」 「……日本語で話せェ」 お腹が鳴ってしまった。気づかれただろうかと不死川さんを伺い見るも、何の反応も示していなかったので、聞こえなかったんだとホッとした。 「腹の虫が喚いてやがるぞ。早く食え」 しっかり聞こえとるやん。顔が熱くなるのを感じつつ、「ではいただきます」と手を合わせる。 味噌汁を一口飲むと、芳醇な香りとともに胃へすとんと落ちた。夢中で食べ続けていると、不死川さんは「喉詰まらせるなよ」とぶっきらぼうに言った。 「おいしいです。うちのお母さんが作る料理より、ずっとずっとおいしいです!」 「……そうかよ」 不死川さんはそっぽを向いてしまった。 「家、思い出せねェか?」 「え?」 「母ちゃんも心配してんだろォ」 ああ、そうだ。現実世界の私は今、どうなっているんだろう。プールで足を滑らせて、溺れて、そのまま寝たきりの状態になっているんだろうか。だとしたら、この夢から目覚めない理由も分かる。 「夢の中で血を流したこと、ありますか?」 「はァ?」 「ごはんを食べておいしいって思ったことは?」 「何――」 不死川さんの手を取って、 「あたたかいって感じたことは、ありますか?」 そう訊くと、不死川さんはすごい勢いで手を引っ込めてしまった。 「……気安く触るなァ」 「あ、すみません」 ――何もかもがリアルなのだ。おかしな夢。 ため息をつき、食事を続けていると不死川さんは「おい」と言う。 「食い終わったら出掛けるぞ」 「えっ、どこへ?」 「蝶屋敷だァ。お前の体を診てもらう」 「……私は別に、どこもおかしくないですよ」 「十分おかしいだろォが。特に頭だな、頭を中心に診てもらえ」 「ひどい。私、遠慮します。ここにいます」 「男一人の屋敷にそれはまずいだろ、察しろよ」 「いいじゃん別に減るもんでもないし」 「減るだろォがよ色々と!」 怒鳴られ、返す言葉が見つからずにいると、不死川さんは我に返ったように「すまん」と呟いた。 蝶屋敷って、あの毒使いの胡蝶しのぶがいるところだよね。もしかしたら夢から目覚める方法を知ってるかもしれない。 「分かりました。行きますよ、蝶屋敷」 「こっちは引きずってでも連れて行くつもりだァ」 そこで今さらながら自分の体をちゃんと見てみると、白い浴衣を着ていた。 「……これ、不死川さんが着替えさせてくれたんですか? 私が着てた羽織はどこに?」 「別にまじまじと見ちゃいねェ。お前が着てた妙な肌着の上から適当に着せただけだァ。あと羽織は燃やした」 「は、燃やした?」 「鬼の羽織なんざこの家に持ち込むんじゃねェ。ンなもん庭先で燃やしたわァ」 「……過激派すぎて常人には理解できない行動」 「るっせェ! てめえが泣きつくせいで取り逃がした鬼だァ! 羽織ぐらい燃やさせろ!」 ――え。これは、笑うべきところ? そんな子どもみたいなことを、と笑っていいのか、それとも神妙に受け止めるべきなのか分からず、口がもごもごとしてしまう。 不死川さんは立ち上がり、部屋の隅の箱を漁る。 「ほらよ」 不死川さんが放り投げたものが顔面に当たり、間抜けな声を漏らしてしまう。それは童磨さんの羽織だった。 「燃やしてないじゃないですか」 「さすがに勝手にはやらねェわ」 「……一応常識はあるんですね」 「で、燃やしていいかよ?」 「いや、んー、私のものではないのでイエスとは言いがたいですけど……」 「はっきりしろォ」 「でもまあ、確かに。この匂いを追って来られたら大変ですもんね」 羽織の匂いをかぐと、お香の香りがまだ染みついていた。 不死川さんは私の言葉を聞くや否や、羽織を引ったくると、力任せに障子を開ける。障子の向こうには、きちんと整えられた庭があった。不死川さんはその庭へ下りると、腰の刀を抜き、羽織を宙へ投げたと思ったら一瞬でそれを細切れに刻んだ。そしてどこからともなくマッチを取り出し、火を放つ。 ――うそでしょ。この人、本当に燃やしたよ。 「お前、これ持っとけ」 燃え盛る炎を背景に、不死川さんは振りかぶる。何か投げる気だ。全力投球のフォームに恐れをなして、私はぎゅっと目を閉じる。 しかしそれは、想像よりも優しい衝撃だった。ぽすん、と膝に落下したのは、薄紫色の巾着のようなもの。 「何ですか?」 「藤の花の香り袋」 「香り袋……えっ、私、臭いですか?」 「違ェわ!」 不死川さんはずんずんとこちらへ近寄って来ると、香り袋をしっかりと私の手に持たせた。 「稀血なら持っとけ。鬼除けになる」 なるほど。言われてみれば、これは見たことがある。鼓の鬼のエピソードで、炭治郎の鴉が吐き出してたやつだ。稀血の少年に渡してた。 ――藤の花って、実際に見たこともなければ嗅いだこともないけど、こんなに甘くてやさしい香りなんだ。 「まだ食えるか?」 香り袋をくんくんと嗅いでいると、不死川さんが不意にそう言った。 「え?」 「食後の茶でも淹れてやる」 「は、え、優しくないですか?」 「お前とはこれで最後になるかもしれねえからなァ」 そう言いながら奥へと消えて行く"殺"の背中を、私は口をぽかんと開けたまま見送った。 不死川さんはすぐに戻ってきた。小さなお盆には湯呑みと、おはぎが載っている。 「あ、おはぎだ」 「嫌いか?」 「おばあちゃんのおはぎが好きです」 「ばあちゃんのおはぎじゃなくて悪かったなァ」 「……あの」 「あ?」 「不死川実弥がここまで親切だなんて私知らなかったんで、あんまり優しくされるとちょっと困るんですけど」 「わけ分かんねェこと言うな。あと呼び捨てすんな」 「あ、すみません」 「困るって、なんでだよ?」 「だって……不死川さんはタミちゃんの推しキャラだから」 「伽羅? タミちゃん?」 「こんなに良くしてもらうと、不死川さんのこと好きになっちゃうじゃないですか」 ――タミちゃんが好きなキャラを、私も好きになってしまう。それは申し訳ない気がする。イカれキャラ枠だとか言っちゃったし。でもきっとタミちゃんは、実弥さんの魅力が伝わってうれしい、と笑うのだろう。 「うるせェ女……」 ふと見上げると、不死川さんは唇を結び、ほんのり頬を赤らめているように見えた。 「えっ、うそ、顔赤くなってません? なんで?」 「なってねェわ! お前もう喋んなァ!」 不死川さんはそう声を上げながら、おはぎを手に掴み、私の口に押し込めた。 うそでしょ、過激派すぎません? そんな言葉も出てこない。うっ、と喉が詰まる。予想外の展開だったのか、不死川さんは目を見開き、私の背中を激しく叩く。 痛いよ、不死川さん。不死川さんが何か言っているけれど、何も耳に入ってこない。不死川さんの指が私の口に入ってくる。喉に詰まった餅米を取ろうとしているらしい。視界が暗転していく。 ――おはぎで死ぬのか、私。ばいばい不死川さん。 それは、無機質な白い天井だった。体をゆっくりと起こし、周りを見る。ここは、病院? 部屋のドアが開く音がして見やると、そこではタミちゃんが目を大きく開き、固まっていた。 「タミちゃん」 おっす、というふうに手を振ると、タミちゃんは顔をくしゃりとさせた。 「ちゃん!」 そうして涙をぽろぽろ流しながら駆けてきて、その勢いのまま抱きついてきた。 「良かったあ、良かったよぉ……ちゃんプールで溺れて、それから目覚まさなくって……」 「どのぐらい眠ってた?」 「丸一日だよぉ」 あ、なんだそんなもんか。泣くタミちゃんをよそに、私の頭は冷静だった。 やっぱり夢だったんだ。長いし、感覚がリアルで、妙な夢だった。 タミちゃんは私の顔を見て、首を傾げる。 「ちゃん、何か食べた?」 「え?」 「口の横にあんこ付いてるよ」 そう言われた時、ふわりと甘い香りがした。腰元の違和感に気づいて、布団の下に手を入れ、ポケットを触る。何か入っている。手を突っ込んで取り出すと、それは、藤の花の香り袋だった。 ――夢じゃ、なかったのかもしれない。 何なのか分からない。けれど確かに言えるのは、どこかで何かが起こり、会うはずのない人たちと出会ったということ。 ぼうっとしたまま、自分の口元に付くあんこを掬って、そっと舐めてみる。 「……あっま」 (2021.04.18) メッセージを送る |