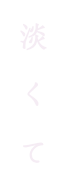
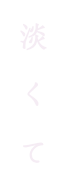
|
うまい飯を出してくれる藤の花の家があると聞いて訪れたのが始まりだった。実弥が生まれた京橋区にあるその家は、小料理屋を営む傍ら、藤の花の家紋を掲げて、鬼殺隊士を受け入れていた。 その家の娘で、病で伏せりがちな母親の代わりに店を切り盛りしているのがだった。生まれがすぐ近くで、歳の頃は同じ。それを知ると、は「どこかですれ違っていたかもしれませんね」とほほ笑んだ。 実際に、実弥は初めてと顔を合わせたとき、懐かしさがこみ上げたのだった。もちろんそれをに伝えることはなかったが、本当にどこかで会ったことがあるのかもしれない、とすら思っていた。 実弥がこの店へ立ち寄るのは、決まって夕方だった。店を開ける準備をしているは、いつも笑って迎えてくれる。 任務前に軽く腹ごなしをするつもりが、に勧められるまま、いつも食べすぎてしまう。どちらかといえば腹が減っているのは任務明けなのだが、そのころには明け方になっているので、店に母の看病に働き詰めのを朝早くから起こすのも悪いと思い、この時間に訪れるのだった。 「遠慮しないでくださいね。ここは藤の家なんですから」 いつものように店へ訪れた実弥に、はそう言った。全てを見透かしたようなその言葉に、実弥は目を見開く。 「もしお腹が空いて倒れそうだったり、万一お怪我をしてつらかったりしたときには、ためらわずにうちへ来てください。確かにここは他の藤の家と比べると狭いですけど、不死川さんお一人ぐらい受け入れることなんて朝飯前なんですからね」 皿に料理を盛り付けながら「ね?」と言うに、実弥は「おう」と短く返し、首を掻いた。 もともとこの店の辺りは京橋区でも栄えていて、実弥が幼いころ暮らしていた裏長屋からは離れている。それでも、もう近寄ることもないと思っていた町だ。いい思い出よりも、つらい記憶の方がはるかに多い。それでもの店を知ってからは、吸い寄せられるように足を運んでしまう。何がそうさせるのか、実弥は自分でもよく分かっていなかった。 「おーっす」 不意に店の戸が開き、暖簾をくぐって大男が現れた。その姿に、実弥は顔を強張らせる。 「宇髄……」 宇髄は実弥を見ると一瞬目を丸くしたが、すぐに口元を緩め、にやりと笑った。 「不死川じゃねぇの。なんだお前、さっそく来てたのかよ」 そのまま実弥の隣に腰掛けると、「いらっしゃいませ」とほほ笑むに向けて、宇髄は言う。 「俺がの店教えてやったの。こいつ、野郎の一人暮らしだからよ、まともなもん食ってねぇんじゃないかって」 「食ってるわァ! なめんじゃねえぞ!」 「相変わらずの狂犬っぷりだなぁおい」 愉快そうに笑う宇髄に、実弥のこめかみには青筋が立つ。しかしの方を見ると、かすかに首を傾げながら、少し心配そうな表情を浮かべて成り行きをうかがっている様子だったので、実弥は怒りをぐっと堪えた。 宇髄はそんな実弥を横目に、懐から取り出したものをへ差し出す。 「忘れねーうちに、はいこれ」 「あ! ありがとうございます。もう香りが薄くなってきていて、不安だったんです」 はそれを大事そうに受け取る。実弥は首を伸ばしてそれが何かうかがい見ると、思わず、 「おい、それって……」 と呟くように言う。 が手に持つそれは、藤の花の香り袋だった。 「もしかしてお前、稀血なのか?」 「みたいです」 はそう言って、困ったような笑みを浮かべた。 この家が藤の家紋を掲げた理由と関わりがあるんだろうと思ったが、実弥はそれ以上何も訊かず、代わりに宇髄へ向けて舌打ちをする。「は?」と眉根を寄せる宇髄。実弥はそれを無視して、に言う。 「足りねえよ。あと十個ぐらい持っとけェ。俺が明日にでも持って来てやるから」 は手で口を覆って、くすくす笑った。 その後、は「少しお待ちを」と言い残し、裏へと消えた。 二人きりになり、気まずい思いを抱える実弥とは反対に、宇髄は頬杖をつきながら実弥の横顔をまじまじと見つめている。そんな宇髄に、「見てんじゃねえぞォ」と苛立つ。 「惚れてんの?」 不意に飛んできたその直球な言葉に、実弥は思わず宇髄の方へ顔を向ける。宇髄はこれ以上ないほどに、にやにやとしていた。 「おい宇髄、てめェそれ以上なんか言ったら――」 「はいはい、刻むんだろ。嫁が泣くから勘弁してくれ」 ひらひらと手を振る宇髄を睨み続けていると、「お待たせしてすみません」とが戻ってくる。その両手には大鉢を二つ乗せていて、実弥と宇髄の前にどんと並べる。すでに並べられていたものと合わせると、十皿近い鉢がずらりとあり、そのどれもが良いにおいを漂わせていた。 「春を感じていただきたくて、旬のものを揃えてみました。お皿に取り分けますので、どれでもお好きなものをおっしゃってください」 あさりの酒蒸し、子持ちカレイの煮付け、菜の花と鶏肉の炊き合わせ、つくしの卵とじ、ふきのとうの天ぷらなど、目の前に並ぶ品々に目を見張る実弥。 「今日はずいぶんと品数が多いな」 宇髄が言うと、は少し照れくさそうに「やっぱりそうですよね」と笑う。 「不死川さんがいらしたら、あれもこれも食べていただきたいと思って、つい張り切っていろいろ作ってしまうんです」 「……え?」 「えっ?」 素っ頓狂な声を出した実弥に、も同じ声色で返す。 そうして目を合わせる二人の横で、宇髄が噴き出す。 「おもしれぇもん見れたわ」 実弥が鋭い目を向けるが、その耳は赤く染まっていて、宇髄はさらにけらけらと笑った。はそんな宇髄に首を傾げている。 「あの、本当は日本酒が合うんですけど、お二人ともこれから任務ですもんね。またお休みのときにでも、ゆっくりと」 そう言ってほほ笑むに、実弥は小さく頷くのだった。 翌日、実弥は藤の花の香り袋を大量に携えての店へ向かった。 戸が少し開いており、中から話し声が聞こえてきたため、実弥は足を止める。 「本当に断ってしまっていいのかい?」 「はい、すみません」 「ちゃんにとっても良い縁談だと思うんだけどねえ」 「ありがとうございます。……でも私、慕っている人がいて」 実弥はそこで、息が止まるのを感じた。そうして香り袋を戸口の脇に置き、音も立てずにその場から去るのだった。 もうこれ以上、深入りしない方がいい。生きる道が違う。やはりここは、近寄ってはいけない町だったんだ。なぜ淡い期待を抱いてしまったんだろう。 愚かな自分が情けなく、実弥はその日、陽が昇ってもなお執拗に鬼を狩り続けるのだった。 あれから何日か過ぎたころ、実弥は連日ろくに食べず、睡眠も取らずに任務に当たっていたため、さすがに体力の限界を感じていた。そうして無意識のうちにの店へ向かっていたことに気づくと、自らの頭を拳で殴った。そのまま頬を殴り、その拍子で切れた口内から血が滲むのを、道の脇に吐き出す。 陽はすっかり落ち、街灯が道を照らしていた。この辺りは栄えている。その分、道ゆく人は他人に無関心だ。それを知っている鬼は、人間に紛れてうろつき、めぼしい人を見つけると路地裏へ引っ張り込んで食うことも珍しくはない。 そう思いつつ、路地裏へと目をやる実弥。そこでは猫が鳴いていた。実弥を見ると、猫の方から寄って来て、足に体をこすりつけてくる。 「なんだァお前、ひもじいのか」 にゃあ、と鳴く猫。実弥は膝を折って、その頭を撫でる。 「生憎、今は何も持ってねェんだ。うまい飯を出す店が近くにあるから、お前はそこに行って、ねえちゃんになんか食わしてもらえ」 そう言った後で実弥の腹が鳴る。じいっと見上げてくる猫に、実弥は力なく笑う。 「ひもじいのは俺も同じか」 猫はふいと顔を背け、路地裏へと戻って行った。実弥は肩透かしを食らったような顔でその後ろ姿を見ていたが、「見切りをつけられたか」とひとりごち、立ち上がる。 しかし猫はすぐに戻って来た。その口には、藤の香り袋をくわえている。実弥はそれを目に映した途端、刀に手をかけ、路地裏へと駆けた。 ――。 街灯のあかりが届かないほど奥深くに、香り袋やその中身が散らばっていた。そんな中でうずくまる背中を見つけ、実弥は立ち止まる。 「不死川さん」 振り向いたその人は、だった。蒼白な顔をして、腕を押さえている。実弥は刀を鞘に納め、駆け寄る。そうして震えるその体を引き寄せた。 「やられたのか」 「ごめんなさい、ごめんなさい」 の腕からは血が流れている。鬼の爪でやられたのだろう、三本線がくっきりと刻まれていた。実弥は懐から包帯を取り出し、その腕をきつく結ぶ。 「ものすごくしつこい鬼で、香り袋を投げつけても諦めてくれなくて……でも袋を破って中身を撒きつけたら――」 「もう何も言うな。傷はそこまで深くねェ。早く医者に」 「だめなんです私、早く行かないと……」 は実弥の手をほどき、立ち上がろうとする。 「お医者さまを呼びに……母の体調が悪化して――」 「おい!」 実弥はの脇腹に手を回し、体をぐっと寄せる。は実弥を見上げ、力なく言う。 「助けて、不死川さん」 そうして気を失ってしまった。実弥はを抱き上げ、鋭い眼光で前を向くと、路地を駆け抜ける。 「不死川さん、これ母からです」 店を訪れた実弥に、は竹皮の包みを差し出した。 春も終わりに近づくころには、の怪我もすっかり全快に向かっていて、今では店にも立てるようになっていた。母親も容体が安定し、たまに料理を振る舞えるほどに回復したようだった。あの路地裏にいた猫も、のもとに住み着くようになった。 「開けてもいいかァ?」 「ぜひぜひ」 実弥が包みを開くと、そこにはおむすびが三つと、漬物が添えられていた。すかさず猫が近寄り、物欲しそうに鳴く。「こら食いしん坊」とが猫を引き寄せる。 「たけのこご飯のおむすびです。母のは絶品なんですよ。任務中にお腹が空いたら食べてくださいって」 「……遠足に行ってるわけじゃねェんだ」 は声を上げて笑った。そんなを横目で見やりながら、実弥は言う。 「おい、俺が言ったことちゃんと守ってるんだろうなァ?」 「夜は絶対に出歩くな、家でも店でもずっと藤の花の香炉を焚いておけ、香り袋は毎日取り替えて持てるだけ持ち歩け」 つらつらとそう唱え、は「完璧にやってます」と大きく頷いた。 を襲った執念深いその鬼はあの後、それ以上に執念深い実弥が見つけ出し、首を斬った。 「不死川さんは私たち親子にとって、命の恩人です」 あの夜、実弥は医者へ駆け込みを託すと、すぐにの家へと走り、母親を背負って最寄りの医者へと連れて行ったのだった。 も母親も、それからは実弥のことを「命の恩人」と言い、は以前にも増して大量の料理を振る舞うようになった。今も鰆の味噌漬けを頬張っている実弥を、はにこにことほほ笑みながら眺めている。 「そんなことばっか言ってやがると、好きな男に勘違いされちまうだろォがよ」 実弥がぽつりとそう呟くと、は目を細めた。 「……宇髄さんに変なこと吹き込まれました?」 「いや、別に――」 「やだ宇髄さんったら本当に……! 絶対に言わないでって約束したのに」 は顔を真っ赤にしながら慌てふためく。宇髄、と実弥は首を傾げる。 先日の柱合会議で顔を合わせたとき、妙ににやけていた。今思い返せば「鈍い者同士、仲良くやれよ」と背中を叩かれたが、あれは――。 「……え?」 「えっ?」 もしかして、という淡い期待がよぎったとき、実弥は素っ頓狂な声を出した。も同じ声色で返す。 ――も俺を。いや、まさか。 「そんなわけねえか」 実弥はふっと笑って、再び鰆の身を箸で摘む。 「あの」 遠慮がちにそう言うを見て、実弥は「ん」と短く返す。 「きっと不死川さんはたくさんの方からこう思われてるでしょうし、私なんかがこんなことを言うのは本当に恐れ多いんですけど……」 「どうしたんだァ?」 「あ、鰆、おかわりしますか?」 「は? 鰆?」 「いえっ、あ、違う」 は自分の手のひらを握り合わせ、そわそわと体を揺らす。 「変なやつだな」 そう言って実弥が笑うので、は固まった。 「笑った顔、初めて見ました……」 「そうだったかァ?」 「好きです」 しん、と静まり返った店内に、実弥の手からこぼれた箸が床へと落ちる音だけが響く。そしてその音で、猫がにゃおんと鳴く。 赤く染まる頬を両手で覆い、おそるおそる実弥を見ている。その目は緊張のせいなのか、涙で潤んでいる。 実弥は机に肘をつき、口元に手を当てる。そうしてへ視線をやると、 「そんな怖がるんじゃねェよ。安心しろォ」 「……え?」 「だが、今から言うこと、宇髄には言うなよ」 耳まで赤く染めているのは実弥も同じことだった。実弥の言葉に、は何度も頷いた。 そうして実弥の唇が紡いだ三文字に、は涙するのだった。 実弥にとってもう近寄るまいと思っていた町が、また帰りたい町へと変わった。変えてくれた。きっと傷は完全に消えるものではない。抱えて生きていく覚悟はできている。それでも、つらさや苦しみをゆっくりと、少しずつほぐしてくれる存在を見つけたから。 ――好きだ。 (2021.04.13) メッセージを送る |