|
雨ばかり降る季節になった。こんな天気じゃ、勤めはじめたばかりのお店に向かう足も気分も、余計に重たい。ふと足を止め、傘の向こうに広がる曇天の空を見上げてため息をついた。 誰にも話せないことが、私には多すぎる。 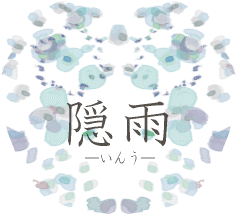 人生初のバイトはファーストフード店の販売員だった。参考書を買うお金欲しさに始めた。髪に染み付く油のにおいにも慣れ始めて、愛想笑いも板に付いて来た頃、両親が離婚した。父親はろくに働きもせずにお酒ばかり飲んで、母親は酒癖の悪い父親に悪態を吐きながら朝から晩まで働いている。そんな崩壊しかけた家庭だったから、二人が離婚したからと言って今さら嘆き悲しんだりはしなかった。 ただ、家計がいっそう苦しくなることにはさすがに戸惑った。と言うのも、私を引き取ったのが甲斐性も何も無い父親だったからだ。父親は「捨てられたのは俺だけじゃなかったな」と歯をむきだして笑った。母は過去を捨てて新しい人生を歩みたかったんだと思う。 でもそんなこと、今はどうだって良い。なんとかお金を稼いで生活していかないと。高校だって今までみたいに普通に通いたい。周りに哀れだなんて思われないためにも、中退は絶対にしたくない。私は、可哀想なんかじゃない。 時給850円のファーストフード店は辞めた。そうして年を誤魔化してキャバクラで働き出したのが、つい先月のことだった。両親が離婚したことも、もちろんキャバクラで働いていることも、誰にも言っていない。学校では絵に描いたような優等生である私から夜のにおいを嗅ぎ付ける人なんて、誰一人いなかった。唯一の友達である神楽ちゃんも、何ひとつ勘付いていない。 どこかで見憶えのある姿形に、私はとっさに視線を反らした。 店に入りたてで化粧の仕方もろくに知らなかった私に、どういう風に化粧をするのかや髪はどこでセットするのかなどを教えてくれる先輩キャバクラ嬢がいた。いわば教育係のようなものだ。そんな彼女にヘルプに呼ばれて席に着くと、その人が居たのだ。 ――神楽ちゃんの、お兄さん。 「あれ?神楽の友達だ」 俯く私の顔を覗き込んで、「やっぱりそうだ」と言った。向かいに座る先輩キャバ嬢が「大学の友達のお兄さん?」と訊いた。彼は大学という言葉に首を微かに傾けたが、私が「そうです」と慌てて答えると、理解したような目でこちらを見て、そうして笑った。私は大学生と偽って働いているのだ。先輩は私と神楽ちゃんのお兄さんについて話を聞こうとしたが、ちょうどその時他から指名が入り、少し席を外すと言って去って行った。 キャバクラで働いていることは、誰にも知られてはいけないことだった。それなのに友達の兄にバレるなんて。しかし私は自分でも驚くほど冷静だった。 「どーも」 「……どうも」 確か、神威だ。彼の名前は。初めて彼と対面した時、厳めしい名前の割には小ざっぱりした顔をしていてずいぶん不釣合いだなあと思った。今も、どこかあどけなさを残す顔でバーボンなんかを飲んでいるから、違和感を感じずにはいられない。しかしスーツは存外似合っている。 「いいの?こんな所で女子高生が働いちゃって」 グラスの中の氷を指で押しながら、神威さんは愉快そうに言った。 「そちらこそ。いいんですか、こんな所で男子高生が遊んでて」 「罪が重いのはそっちだよー?」 軽やかな口調でそう言われて言葉を呑んでいると、神威さんはこれもまた軽やかに笑った。 聞きたいことはたくさんあった。でもそれを問えば私の事情も聞かれると思ったので、やめにした。 「よく私だって気が付きましたね」 「まあね」 「ほんの二回しか顔を合わせたことが無いのに」 神威さんは口角をきゅっと上げた。そうしてグラスを傾けながら言う。 「眼鏡掛けてる方が僕は好きだけどな」 私はとっさに俯いた。 いつもの私は髪を二つに結って眼鏡を掛けている。そんな“いつもの私”しか知らないはずの神威さんが、髪を巻いて派手な化粧をしたキャバクラ嬢を、いとも簡単に“私”だと見破ってしまった。 「……ありがとう、ございます」 神威さんは微笑んだ。 初めて神威さんに会ったのは、神楽ちゃんと一緒に帰っていたとき。神楽ちゃんの家へ向かう方と私の家へ向かう方との分岐点で私たちが雑談していると、神威さんがそこを通りかかったのだ。一応制服を着ているのだが、決してマジメとは言えない着こなし方だった。私はスカートも規則通りに膝下までの丈なのだけれど、神威さんの学ランの丈は私と同じく膝下まで長さがあったし、何か文字が刺繍されていた。そんな格好をしているのに、「神楽の友達?俺は神威。妹と仲良くしてくれてありがとね」と言って笑ったから、私は思わず噴き出した。厳めしい服装と清々しいその笑顔や言葉に、愉快なギャップを感じたからだ。 二度目に会ったのは、私がファーストフード店でのバイトを終えて駅に向かう途中の道だった。不意に声を掛けられて振り向くと、強面の男性数人が立っていて、私は肩を強張らせた。でもすぐにその中から神威さんが出て来て「こんばんは」と笑んだので、ひどく安心してため息を吐いた。そんな私に「もしかして怖がらせちゃったかな?ごめんね」と神威さんが言うと、その後ろで男性たちが「すみません」と一斉に頭を下げた。私は彼らを率いているのが神威さんなのだと察して、微苦笑した。 カラン、という乾いた音でふと我に返ると、神威さんはこちらにグラスを突き出していた。 「グラス、空いたよ。注いでもらえる?ちゃん」 「です」 ボトルを取りながら言うと、神威さんは「?」と首を傾げた。 「……私の源氏名。ここではそう呼んで下さい」 「ああ、そっか。ごめんごめん」 注がれたバーボンを飲む神威さんの横顔を眺めていると、不思議な気分になった。ここがどこで自分が誰だかが一瞬分からなくなったのだ。神威さんの口の端から漏れたバーボンが喉仏を伝い、シャツの中へ消えてゆく。 「こぼれちゃった」と言われて、意識が引き戻された。急いでおしぼりを渡そうとすると、誤って取り落としてしまった。拾い上げようとテーブルの下へ体を折る。神威さんは足を退けてくれた。そこでふと神威さんの足元に目が行った。 「裾、濡れてますよ」 「雨が降ってたからね」 おしぼりを拾って身を起こすと、神威さんは「ご苦労様」と言った。私はそんな彼に新しいおしぼりを差し出す。そうか、外はまだ雨が降っているのか。そんなことをぼんやりと考えながら。 横目で神威さんを見ると、グラスを舐めながらどこか遠い目をしていた。いつも微笑みを絶やさない人だと思っていたので、彼もそんな表情をするのかと驚いて、 「神威さんって不思議な人ですよね」 思わずそう口にしてしまった。 すると神威さんは、 「君もね」 と、笑った。 そうだ。この人の笑顔は感情が読めない。笑っておけばいいと思ってるんだろうか。そんなの、笑顔の安売りで客を引っ掛けてるキャバ嬢と同じだ。 「神威さんって、どんな人?」 昼休みの教室は揚げ物やソースのにおいが充満していた。雨が降り続けているので窓を開けて換気も出来ない。ただでさえ生乾きのつんとした匂いが蔓延していた所に、様々な食べ物のにおいが混ざり、空気が重い。そんなムッとする教室の中で、私と神楽ちゃんは机をくっ付け合ってお弁当を食べていた。卵焼きを突きながら不意にそう訊くと、神楽ちゃんは瓶底眼鏡の下で目を丸くさせた。 「どうしてそんなこと訊くアルか?」 「えっと……ただなんとなく気になって。兄弟がいるってどんなだろうって、興味があるし。ほら私って一人っ子じゃない?だから、さ」 普段口数が多い方ではない私がつらつらと言葉を並べたので余計怪しまれるかと思ったが、神楽ちゃんは「ふーん」と頷いて唐揚げを頬張った。 「兄弟がいたって別に良いことはないアルヨ」 「そうなの?でも、家の中が賑やかじゃない?」 「うーん、別に。アニキめったに家に居ないから、私いつも一人アル。まあその分チャンネル独占出来るのは良いけどネ」 「え、神楽ちゃんの家って……」 そこで言葉を切って、私は謝った。立ち入ったことを訊いてしまいそうになったからだ。こういう“家庭の事情”に、私は人一倍敏感だった。 「家はアニキと私の二人暮らしアル。マミーは病気で私が小さい頃に死んじゃったし、パピーは行方知らずだから」 神楽ちゃんが私の途切れた言葉を拾って平然とそう答えたので、私はどう返したら良いか分からず、「そうだったんだ」と呟くように言った。学校ではいつも一緒にいるけれど、これは初めて知る事だった。第一、神威さんと帰り道で出くわすまで、私は神楽ちゃんに兄弟がいることさえ知らなかった。さっきは当然のように言ったけれど、神楽ちゃんだって私が一人っ子だったことは今の今まで知らなかったはずだ。私たちは今までそういう家庭の話は一切してこなかった。もしかすると、私がそういった類の話題を避けていたことを神楽ちゃんは察して、気を回してくれていたのかもしれない。 そのお弁当も自分で作ったのかな。タコ足のウインナーや唐揚げ、梅干しの乗ったご飯などが詰まったお弁当箱を見ていると、少し胸が痛くなった。ついさっきまで、あのお弁当は神楽ちゃんのお母さんが詰め合わせてくれたものだと当たり前のように思い込んでいたから。羨ましくて少し妬ましくさえ思っていた自分を恥じた。 「アニキは」 その声で我に返り、お弁当箱から視線を外して神楽ちゃんの顔を見た。 「人の弱みにつけ込んでとことん利用し尽くす男ネ。そうやって生きる屍みたいになってった女、私たくさん知ってるアル」 それってどういう意味?そう訊こうと口を開きかけたとき、フォークの先からウインナーを落としてしまった神楽ちゃんが叫び声を上げたので、言葉を呑んだ。床に落ちて消しゴムのカスが引っ付いているウインナーをそれでも食べようとするので、「せめて洗っておいでよ」と慌てて止めると、神楽ちゃんは「ナイスアイディア!」と教室から飛び出して行った。 ため息を吐いて窓の外を見遣ると、雨脚は先ほどと比べて強くなったようだった。濡れた神威さんの裾を思い出しながら、ミニトマトを齧った。甘酸っぱい。 神威さんが再びお店にやって来たのは、それから数日後のことだった。 私は指名を受けて神威さんの席についた。今日は黒のジャケットにジーンズ姿だった。裾は濡れていなかったが、左肩に雨粒が付いていた。ハンカチでそっと拭うと、神威さんは「ありがと」と笑った。その笑顔を見上げながら神楽ちゃんの言葉を思い起こすも、果たしてこの人にそんな事が出来るのだろうかと目を細めた。こんな私を知ったら「見た目に惑わされてる」と神楽ちゃんは怒るのだろうか。 バーボンが運ばれて来て、私はグラスに氷を入れてお酒を注ぐ。続いてボーイが私の傍らにジンジャーエールを置いた。 「酒は飲まないの?」 グラスを受け取りながら、神威さんが訊いた。私はもう一つのグラスにバーボンを注ぎ、神威さんの持つグラスに軽く当てた。カツン、と音が鳴る。 「乾杯だけ。未成年なので」 バーボンには口を付けず、乾杯を済ませるとテーブルに戻して、代わりにジンジャーエールのグラスを手に取った私に神威さんは言った。 「そこはちゃんと守るんだ。なんか感じ悪い」 その声がいつもの軽やかさを含んでいなくて、思わず眉根をひそめた。神威さんの方に顔を向けると彼はにこりと笑む。気を悪くさせてしまったのかもしれない。謝ろうとすると、神威さんはボーイを呼んで、そうして耳打ちするように何かを伝えたようだった。ボーイの後ろ姿を見送りながら、どう会話を切り出したら良いのか分からず黙り込んでいると、神威さんは愉快そうに笑った。 「ちゃん、何か話してよ」 「……話題が見つからなくて」 「そんなんじゃセンパイに叱られるよー。ここは酒と会話で客を楽しませる所なんだから」 それでも私が押し黙っていると、神威さんは「じゃあ俺が話を振ってあげる」と言った。 「いつからここで働いてるの?」 「――先月です」 神威さんは短く「へぇ」と言った。 「私も訊いて良いですか」 「どうぞー」 「いつからこういうお店に通ってるんですか?」 それは神威さんがこの店に現われた時から抱いていた疑問だった。いつから、どうして、高校生が一人でこんな夜の街に。自分のことを棚に上げて置いて自分からこんなことを訊くのも、と思って言えなかったが、先にそういう話題を振って来たのは神威さんだ。 「忘れた。でもこの店に来たのはこの間が初めてだよ」 「どうして、キャバクラなんですか?」 被せるようにそう尋ねた私に、神威さんは手を突き出して言った。「次質問するのは俺」。 「優等生の君がどうしてこの仕事を選んだの?」 それは、先ほどの私の質問がそのまま返されたようだった。どうしてキャバクラなの。 不意に、ファーストフード店で働いていた頃を思い出した。参考書を買うお金が欲しいという、今考えればそんな可愛くて幸せな理由で始めた仕事だった。お客とはカウンターを隔てて接すれば良いだけで、酔っぱらった客に体を触られる心配も何も無い。売上のために営業の電話やメールをしなくても、ジャンクフードを求めてお客は勝手にやって来る。そうして稼いだお金は父親の酒代ではなく、全て自分の為に消えていく。あの頃自分はとても惨めだと思っていたけれど、今思えば何て事は無い。むしろ何を悲劇のヒロインぶっていたのかと、呆れさえする。 「……だって、こうでもしないと、生活していけないから」 同情だけはされたくなかった。だから毅然としてそう言ったつもりだった。けれど、出てきた声は自分でもどうしようもないほど擦れて、弱弱しく響いていた。 神威さんがどんな反応を示しているのか知りたくなくて俯いていると、「お待たせいたしました」と言うボーイの声が聴こえた。それでも俯いたままでいると、ちゃぽん、と何かが液体の中に落ちる音がして、思わず顔を上げた。 「これ食べてみなよ」 神威さんが差し出したのは私のジンジャーエールで、そのグラスの底には先ほどまで無かった赤い球体が沈んでいた。私は目を細める。 「これって……カクテルボールですよね」 カクテルボールとはテキーラやウォッカベースのカクテルをゼリーにした物で、最近はどこの店でも流行っているらしく、お客もキャストも一緒になって頬張っている姿を店内でもよく目にした。 「うん。美味しいよ。コラーゲンも入ってるから肌が綺麗になるって、女の人は喜んで食べてる」 「私ダメなんですって、お酒は。怒られます」 「誰に?店長?本当は高校生だってバレたら、怒られるどころじゃないよね」 さらりと放たれたその言葉に、体が強張った。 もしかして、脅されているんだろうか。ぐいぐいとグラスを頬に押しつけられる。「ねえ、そうだよね」と言う神威さんは、唇にはうっすらと笑みを浮かべているが、目は全く笑っていない。 怖い。本能がそう叫んだ。 「大丈夫。ほら、誰も見てないから」 言われるがままにグラスに口を付け、一気に飲み干した。最後に残ったゼリーを口に含むと、イチゴの味が広がった。喉を通るときに甘さとは違うものを感じて、初めて知るアルコールの味に目が眩んだ。グラスが空くと、今度は紫色の球体を入れて、私に渡してくる。逆らってはいけない気がして、私は神威さんが次々と入れる色とりどりのゼリーを全て食べた。 しばらく経つと、体が熱くなってきた。心臓がばくばくと激しく鳴って、息が苦しくなる。思考回路が停止して、何も考えられない。そんな私の隣で神威さんはバーボンを飲み続けていた。私の意識が朦朧とする中で、神威さんはこんなことを言った気がする。 「子どもは親に苦労掛けても良いって言うけど、親が子どもに苦労させるって、どうなんだろうね」 またあの、遠い目をしていた。 「具合悪そうアルな」 顔を上げると神楽ちゃんの顔がすぐそこにあって、思わず身を引いた。 授業の中休みで、教室は生徒たちの喋り声で溢れかえっていた。机に肘を付いて頭を抱えていると、不意に神楽ちゃんに声を掛けられたのだ。神楽ちゃんは私の机に腰掛けながら「どした?」と訊いた。 「う、うん……ちょっと頭が痛くて」 「二日酔いアルか?」 すぐに否定すれば神楽ちゃんはニヤリとあくどい笑みを浮かべたので「本当に違うからね」と言ったけれど、声が上擦ってしまった。 「飲酒なんてはいつからそんなワルい女になったアルか?」 「神楽ちゃん!」 声を張ると重い頭にがんがんと響いて、胸の気持ち悪さが増した。 必死な私に「分かったヨ。ごめん」と神楽ちゃんは謝った。神楽ちゃんは何も間違っていないのに、謝らせてしまった。私は確かに二日酔いだったし、純粋な彼女にとってキャバクラで働く私はきっとワルい女だ。何も間違っていない。 神楽ちゃんは眼鏡を外して、スカートの裾でレンズを拭う。その横顔がどこかしょんぼりとしていたので、私は自分の眼鏡ケースから眼鏡拭きを取り出し、「これ使って」と差し出した。 「あんがと」 やっぱり兄妹なんだなと思った。そう言って笑った神楽ちゃんの顔と、神威さんの微笑みが重なって見えたから。神楽ちゃんは普段眼鏡を掛けているからあまり分からないけれど、こうして外してみると、そこには神威さんと同じ瞳があった。 「この間の話なんだけど……」 「ハナシ?」 「神威さんの……」 眼鏡を拭く神楽ちゃんの手元を見据えながら、「ああ」とどこか気の無い返事をするその声を聴いていた。 「兄貴はバイトも何もしてないのに、なぜか金持ちアル。最初はヤツの舎弟達から巻き上げてるのかと思ってたけど、ほんとは違ったネ」 そこで神楽ちゃんは一呼吸置いた。私に眼鏡拭きを返して、瓶底眼鏡を再び耳に掛ける。 心臓の鼓動が速くなる。 「あいつ、女達から金貰ってる。というか、貢がせてるアル。その金で毎日遊び回ってるネ。私はパピーが送ってくれるお金で生活切り詰めながら暮らしてるのに。酢昆布だって週に二箱でガマンしてるアル」 思考回路が鈍っている。神楽ちゃんの言葉が耳から脳までたどり着くのに、しばらく時間がかかった。これも昨晩のアルコールのせいだろうか。お酒の味なんて、まだ知りたくなかった。 天気予報によれば、来週には梅雨が明けるらしい。それでしばらく雨とはお別れだ。 雨がアスファルトを打つ音しか聞こえない夜の住宅街は、どこか不気味だ。私はそんな中、神楽ちゃんといつも別れる岐路で傘を差して突っ立っていた。左の道に行けば神楽ちゃんの家、右の道を行けば自宅がある。 私はその分岐点に生えるカーブミラーを見上げたまま、雨粒にまみれた鏡にかろうじて映る自分の姿を眺めていた。いつかお店に来たファッション関係の仕事に就いているお客が、オレはスウェット姿のまま外を出歩くような奴は許せないんだと声を荒げて言っていた。あの時の言葉はまさに今の自分に向けられている。無造作に束ねられた髪に眼鏡で、よれよれのシャツにスウェットを履いてコンビニ袋を片手に提げている私を見たら、あのお客は何て言うんだろうか。でもまあ、もう二度と会うこともないだろうけれど。 「店辞めたんだね」 振り返るまでもなく、カーブミラーに映ったその姿で、声の主が誰なのか分かった。突然現われたその人に別段驚くわけでもなく、私は「はい」と答えた。 「残念だな。ちゃんのこと結構気に入ってたのに」 神威さんは私の隣に立つと、こちらを覗き込んで来た。その姿に思わず息を呑む。 「どうして傘を差してないんです?」 「傘、無かったから」 髪の先からは次から次に水滴が垂れている。頭のてっぺんから足先まで濡れているのに、変わらず笑みを浮かべて平然と立っているので、呆れるより先に体が動いた。腕を伸ばし、自分の傘に神威さんを入れる。ここ最近は毎日朝から晩まで雨が降っている。なのに傘を持たずに出歩くなんて。「風邪ひきますよ」と言う私に構わず、神威さんは続ける。 「生活は大丈夫なの?」 「……私がキャバクラで働いてること、父が知って。そしたら少し心を入れ替えたみたいで、働くようになったから」 甲斐性の無い父だけれど、娘に対する情はまだ残っていたようだった。キャバクラを辞めた後で、実は水商売をしていたのだと告げると、父は顔色を変えた。てっきり「なんで辞めちまったんだ。俺の酒代もっと稼いで来い」だの「女は楽に金が貰えて良いよな」なんて言うんだろうと思い込んでいたけれど、彼の口から出たのは「悪かったな」という、予想すらしていなかった言葉だった。その日を境に父は変わった。飲酒量も減って、職安にも通うようになり、定職に就いた。私も再びあのファーストフード店でバイトを始めた。 「そっか。良かったね」 神威さんは朗らかに言った。 私は少し背の高い神威さんを見上げながら、唇を噛み締めていた。 「やっぱり俺は、眼鏡を掛けてるちゃんの方が好きだよ」 唇を噛む力が緩んだ。くらりと目まいがする。私は力なく顔を下げた。 初めてアルコールを体に入れたあの日から毎日、私は隠れてお酒を飲んでいた。このコンビニのビニール袋に入っている缶ビールや缶チューハイは、父の為のものじゃない。自分のものだ。酒に酔ってしまえば、何も考えられなくなる。何も考えなくて良い。それを教えてくれたのは他でもない、神威さんだった。 「やめてよ……ヒドい男なんだって…知ってるんだから」 絞り出すように言った。 神楽ちゃんの言葉が耳に蘇る。もっと雨が降れば良いのに。雨音でかき消してくれればいいのに。 「やっと普通の暮らしが出来るようになったの。だからもうやめて。あなたになんか、利用されたくない……」 「利用ってどういうこと?」 「……神楽ちゃんから聞きました。神威さんは女の人たちに貢がせてるって。弱みを握られたその人たちは神威さんに利用され尽くして、生きる屍みたいになってるって」 「だからキャバクラを辞めたの?俺から逃げるために?」 「……そうです」 「神楽の言う事を信じるんだ」 声色が変わった。下げていた視線を上げると、神威さんの顔から表情は消えていた。 「――友達だもん」 「俺はその友達の兄貴だよ」 私は頑なに首を横に振った。そうしながら、もうやめてよ、やめてよ、と馬鹿みたいに繰り返していた。 早くお酒を飲んで、頭をまっさらにしたい。早く缶を空けてしまいたい。また無理矢理にでもカクテルボールを口に押し込められたって構わない。何も考えたくない。誰か私を酔わせてほしい。 「その様子だと俺が何を言っても信じてはくれそうにないね。でもさ、これだけは言わせてよ。俺だって、タダで金を貰ってるわけじゃない。それ相応のモノを払ってる。楽して金が稼げるなんて、そこまで世の中舐めてないよ」 頭が冷静さを取り戻した。 神威さんを見ると、彼は妙な笑い方をしていた。 「神楽には言わないでくれる?あいつは父親が仕送りしてくれてると思い込んでるから。本当はこんな汚れた金で生活してるなんて知らずにね」 ポケットから出された紙幣は、そのまま無造作に突っ込まれていたのかひどく皺が寄っていたし、雨に濡れてぐちゃぐちゃだった。その紙幣を見下ろして、神威さんはまた笑う。自嘲的な笑みだ。 私が言葉を失っていると、神威さんはそれらをポケットに再び突っ込みながら、「あのさ」と口を開く。 「これからも神楽と仲良くしてあげて」 それだけ言うと、神威さんは傘の下から出て、家へ続く左の道を歩いて行く。私はその場に突っ立って、後ろ姿が雨の中に消えてゆくのをただ見つめるだけだった。 しばらく立ち尽くしていた。そうしてコンビニ袋の中からビールをのろのろと取り出し、缶を開けた。ぷしゅ、と空気の抜ける音が響く。缶を逆さまにして、雨に濡れるアスファルトの上に零す。缶チューハイも同じようにして、中身をすべて出した。 感情を殺し続けて笑顔を作るしかなくなった彼は、これからも彷徨い続けるんだろう。私にはもうどうすることも出来ない。誰にも話せないことが、神威さんには多すぎるから。 私がアスファルトに吐き出させた酒は、雨水と一緒になって排水溝に吸い込まれてゆく。その溝の下には、すべてが綯い交ぜになったその液体を大口開けて飲む、したたかに酔った生き物がいるはずだ。 (2011.4.13) |