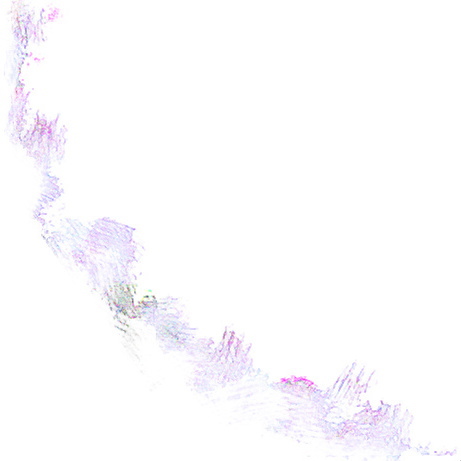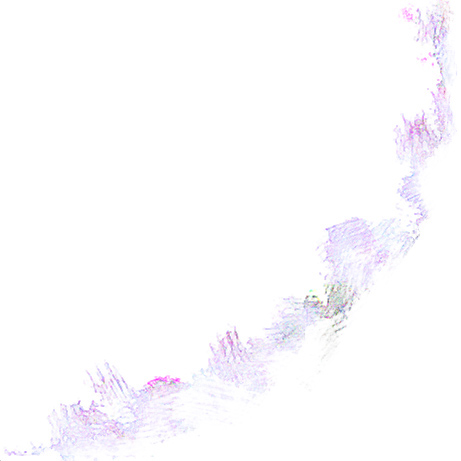
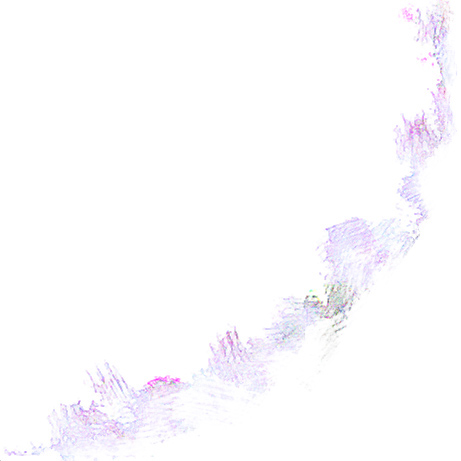
|
泳 ぐ た め に
ああ、やだ。なんで。 思いが顔に現れるよりも先に、足が動いた。踵を返して、もと来た道を引き返す。行き交う人の中に彼らを見たのだ。どうして私の街に彼がいるのだろう。お腹の大きな奥さんをいたわるように身を寄せて歩く彼の姿を思い返し、唇を噛んだ。去り際に彼と目が合った気がする。いっそう強く唇を噛んだ。ああ、やだ。鉄の味。 「逃げただろう」 玄関扉を開けた途端、彼は怪訝な顔でそう言った。 ジェームズが家へやって来るのは月に数回、決まって金曜の夜だった。その曜日の夜だと何かと理由を付けて家を出て来やすいのか、詳しいことは訊いたことが無いから知らないけれど。 「何でこの街で買い物なんかしてたのよ」 「僕の街には本屋が無い」 「ああ、だから絵本でも買いにやって来たってわけ。良かった。私に見せつけに来たのかと思ったわ」 皮肉っぽく言いながらリビングへ向かっていると不意に腕を引かれた。「」。振り返ると、ジェームズが眉根を寄せて私を見下ろしていた。 「お前がこっちを見た途端に逃げるように走って行ったから、妻も不思議がってた」 「そのぐらいじゃ勘付かないでしょう。本当に鋭い人なら、もう私の存在に気付いて怒鳴り込んで来てるわよ」 腕を払うと、ジェームズの手はたやすく離れた。「」。振り返らず、そのままリビングへ駆け込んだ。足音が追い掛けてくる。そのことに心のどこかで安心している自分も、往生際が悪くて笑える。 ソファを避けて窓際まで来ると足を止めた。肩を掴まれ、強引に振り向かされる。ジェームズは困惑するわけでも怒るわけでもなく、ただ眉間に皺を作って私を見下ろす。 なぜだか息が漏れた。それまで入りすぎていた力が抜けて、体が揺れた。そうして弱弱しく言う。 「じゃあどうしたら良かった?何も無い顔をして隣を通り過ぎるなんて、私には無理」 「そのぐらいやって退けろよ。愛人失格だぞ」 「良いわよ失格で」 愛人。執念深さが滲み出てくるような言葉だ。もう長い間こんな関係を続けているのに、未だにこの言葉には慣れない。先ほど彼が放った「妻」という言葉が耳に蘇り、それが頭蓋の内に響く。 ふと、窓の外が気になった。誰かが見ているかもしれない。そんな突発的な不安に駆られてカーテンを閉める。閉めた後で、どうして自分はこんなことをしているのだろうと我に返り、頭を抱えた。いつからこんな、いつまでこんな。 私たちは街外れのパブで出会った。確かあの夜も金曜だった。カウンターで隣り合わせた見ず知らずの青年と意気投合し、会話をしている内に彼は唐突に言った。「幸せなはずなのに、なぜか疲れるんだ」。そう言った顔はひどく疲れきっていた。それから話を続けているうちに、彼に恋人がいることを知った。「学生時代ずっと好きだった人とついに恋人になれたんだけど、彼女に嫌われまいと思って本当の自分を押し殺し続けていたら、自分が一体何なのか分からなくなってきたんだ」と頭を抱えた後、「それでも彼女を失いたくない」と震える声で言った。その話を黙って聞きながら思った。本当の彼の姿が見てみたい。すべての始まりは、そんな私の好奇心からだった。 「――やっぱり、あの時別れたら良かった。あなたが結婚する時に。だって私は不倫なんて……」 「浮気は良くても、不倫には付き合ってられないってわけか。でもあの時、愛人でも良いからって泣きついたのは君の方だっただろう?」 「ジェームズが離れるなって言ったじゃない。あの時、目でそう言ってた」 そう言って肩にまとわりつく彼の指をほどこうとすれば、一層力強く掴まれる。顎をぐいと上げられて顔を寄せられれば、手の平でそれを防いで首を振る。おい、と彼は眉を下げる。 「今日は気が立ってるみたいだな。少し落ち着け」 「ねえ、分かってるの?あなたは親になるのよ、ジェームズ」 引き寄せられた体を離すために胸を押しても、彼は微動だにしない。 「あなたの血を継いだ子があの人のお腹の中にいる。私には、それが許されないのに……」 理性なんてすべて吹き飛んでいってしまったかのように押し倒すのに、抜かりなく避妊具を付ける彼を何度恨んだことか。自分と奥さんとを比べてしまってどうしても惨めさを感じてしまう私に、彼はもちろん気付かない。これが奥さんだったら、きっと何もかもが違う。背中に爪を立てることも許すし、体を気遣って優しく触れるんだろう。抱かれながらそんな取り止めもないことを考えていることだって、気付いてはくれない。 ぐい、と腕を引かれた。ソファへ導かれていることを察すると、私は激しく抵抗した。 「満たされるのはいつもあなただけじゃない!」 胸を拳で叩きながら喚くと、涙がぼろぼろと零れた。叩き続ける手を掴んで制した彼の妙に落ち着いた態度が、私をますます泣かせた。 「私やあの人や子供はどうなるの?あなた以外の人はみんな、虚しいわ」 泣きじゃくる私の顔を、彼は少し身を引いて、けれど腰にしっかり腕を回したままで覗き込んだ。 「あなたって本当に自分勝手で、強欲よ」 そこで彼は、ふっと息を吐くように笑った。その吐息が私の前髪を揺らした。見上げると、眼鏡の奥の瞳が輝いて見えた。私の目が涙で滲んでいるせいかもしれない。 「そうだよ。俺は自分勝手だ。欲しいものだって全部手に入れたいし、一度手にしたら手放したくない」 「……まるで子どもよ」 「そんなこと、もう知ってるだろう?」 片方の口角を上げて彼はいたずらに笑んだ。しかし声色はとても穏やかだった。 「君にはそんな子どもの僕を見せることが出来る。僕のありのままを受け止めてくれるのはだけだ」 そう言って私を抱き締めた。そうして「ほんとだよ」と囁かれれば、もう私は首を縦に振るしかない。 「あと一時間ぐらいしか居られないけど、今日はもう何もしない。ただ一緒に寝てくれるだけで良い」 私はうんうんと頷くだけだった。そうして気付けばソファの上で横たわっていた。ジェームズは額にキスをひとつ落としただけで、本当に何もしてこなかった。ソファに身を寄せ合って、深く沈む。しがみ付くと頭をやさしく撫でられて、不安や惨めさはかき消されていった。 ジェームズとの関係はきっとこれからも続く。彼は、私がいないとバランスを保てなくなって、大切な奥さんを失うことになるということに気が付いているからだ。結局彼の成す事すべては、愛する家族のために。それでも良い。それでも私は彼に求め続けられる限り、応え続ける。馬鹿な女だよなって笑っても良いよ。 |